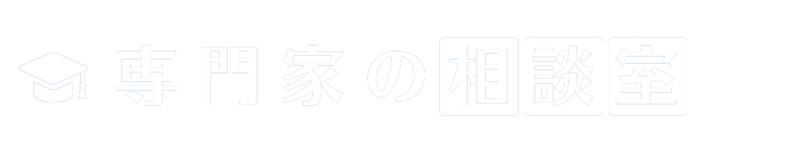事業をしていると、今期の業績がかたまってきた年度末に「少しでも節税できないか」と誰もが考えるのではないでしょうか?
今回は、うまく使えば節税に使える「短期前払費用の特例」をご紹介します。
▼この記事でわかること
・短期前払費用の特例を使えば、前払費用として資産計上していたものを費用にできる
・短期前払費用の特例を使える要件と対象に注意
短期前払費用の特例って何?
短期前払費用の特例とは、「前払費用のうち特定の条件を満たすものは資産に計上せず、支払った時の必要経費・損金にしても大丈夫ですよ」という特例です。
本来翌年度の費用は、当年度の必要経費・損金にはできませんが、
この特例を使えば必要経費・損金にでき、その分だけ所得を減らすことができるため、税金が安くなり節税になるのです。
ただし、注意点など落とし穴も色々あります。
今回は短期前払費用の特例について徹底解説いたします。
前払費用とは役務提供を受けていない前払い
前払費用とは役務提供を受けていない前払いを指します。
と言われても、ちょっとイメージがわきにくいですよね。
ここでいう「役務提供を受ける」は、「サービスを受ける」と読み替えてもらってかいません。
通常、サービスを受ける・対価を払うという行為は、同時期になるパターンが多いですよね。
「レストランで食事をして会計をする」「タクシーを利用して代金を払う」という具合です。
つまり、前払費用とは契約で継続的にサービスを受けるための支出のうち、まだサービスを受けていない分に対応する支出のことをいいます。
ちなみに、税務上は例えば定期購入の水の代金の前払は役務の提供ではなく、商品の購入の前払いであると判断され、前払費用ではなく、前払金だとされています。
参考
前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
(引用:国税庁「短期前払費用として損金算入ができる場合 1.前払費用」)
例えば個人事業主が7月に事務所を借りて、向こう1年分(翌年6月まで)の家賃120万円を7月に支払ったとします。
この場合、7月の支払時は7月分1か月分はすでに役務提供を受けているため賃借料などで処理しますが、8月~6月分の11カ月分は、7月時点では前払費用として会計処理します。
7月の支払時の会計処理
賃借料10万円 / 現金預金120万円
前払費用110万円
その上で8月になれば、その11カ月分の前払費用のうち1か月分を賃借料に振り替えます。
賃借料10万円 / 前払費用10万円
これを毎月繰り返すことになります。
したがって、12月末時点では、1月から6月分の6カ月分が前払費用として残ることになります。
(個人事業主は1月から12月までの期間で決算を組むと決まっているため、この例では1月から6月が翌年分になります。)
前払費用と前払金の違いは?
ここまでをいったん整理しましょう。
前払費用を理解するためには、前払金との違いを考えるとわかりやすくなります。
前払費用と前払金の違いを下表にまとめました。
▼前払費用と前払金の違い
| 前払費用 | 「サービス」に対して前払した費用 サービスをまだ受けていないもの |
| 前払金 | 「サービス以外」に対して前払した費用 実質的に商品購入のことが多い |
短期前払費用とは?
前払費用のうち、支払った日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものを支払った場合は、その前払費用を短期前払費用とよびます。
短期前払費用の特例を使えば支払時に全額損金にできる!
短期前払費用のうち、一定の条件を満たすものは、その支払った時に全額損金すなわち経費とすることができます。
これを短期前払費用の特例とよんでいます。
参考
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。
(法基通2-2-14)
(引用:国税庁「短期前払費用として損金算入ができる場合 2.短期前払費用 ※1:前払費用」)
短期前払費用の特例が使える対象の範囲や要件は?
短期前払費用の特例を使うには、前述のとおり一定の要件を満たす必要があります。
短期前払費用の特例の要件
- 前払費用の要件を満たしていること
- 支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものであること(期間の要件)
- 毎期継続して経費に計上すること(継続の要件)
- 収益と対応する経費ではないこと
以下、それぞれの要件について詳しく見ていきますね。
要件①期間の要件
まずは期間の要件についてです。
保険であれば、4月から3月までの1年分の保険料を3月に支払った場合は期間の要件に該当します。
3月に5月から4月までの保険料を支払った場合ですと、1年の範囲を超えてしまうので要件を満たせない、ということになります。
要件②継続の要件
次にその費用の支払いが規則的に継続していること。
保険料にしても、今年は1年分一括払いにして、来年からは月払いにしよう、というのは認められないので注意が必要です。
収益の計上と対応させる必要があるものは認められないので注意
企業の売上のためにかかった経費など、収益と対応関係にある費用については、特例が認められていません。
たとえばアパートを所有し、それを貸し出して家賃収入を得ている不動産管理会社の場合、『受取家賃』と『支払家賃』は対応関係にあります。
そのため、『受取家賃』は毎月、対応する月の分だけを計上し、『支払家賃』については1年分を一括払いして、「短期前払費用」の特例を適用して翌1年分まで計上する、ということはできません。
短期前払費用の特例が認められる場合と認められない場合
前述の要件をすべてクリアする必要がありますので、短期前払費用の特例に該当するのは、主に以下のような支払いに限られます。
短期前払費用の特例に該当するもの
- 地代、家賃、駐車場代
- 生命保険料、損害保険料
- 保守料
- 特許権、商標権の使用料
- 看板広告代
- レンタルサーバー代
逆に特例として認められないのは、以下のようなケースです。
間違いが起こりやすいポイントのため、注意が必要です。
認められないもの
- 弁護士、税理士などの顧問料
- 雑誌の年間購読料(電子版を除く)
- リスティング広告料
- 転借賃料
- 財テク目的の借入金利息
それぞれ見ていきましょう。
(短期前払費用に該当しないもの)弁護士、税理士などの顧問料
弁護士、税理士などへの顧問料は、毎年変動します。
つまり、時間がかかれば値段があがったり、内容によって変動します。
したがって、等質・等量のサービスではないため、継続の要件にひっかかります。
(短期前払費用に該当しないもの)雑誌の年間購読料(電子版を除く)
雑誌の年間購読料は、サービスの提供ではなく商品の購入であると判断されます。
したがって、前払費用ではなく前払金となるため、短期前払費用の要件を満たしません。
(短期前払費用に該当しないもの)リスティング広告料
リスティング広告は前払しますが、クリックされるたびに課金される従量課金制です。
したがって、継続的に同じ額が計上されるものではないため、継続の要件にひっかかります。
(短期前払費用に該当しないもの)転借賃料
こちらは、先ほどの説明の通りです。
収益に対応する費用になるため、短期前払費用の特例は利用できません。
(短期前払費用に該当しないもの)財テク目的の借入金利息
こちらは借入金利息を支払ながら、それを利用してお金を稼ごうとしているため、収益を得るための費用と判断されます。
したがって、収益に対応する費用であるため、短期前払費用の特例は利用できません。
短期前払費用の特例を使って、税金を減らす方法は?
短期前払費用の特例を使える要件は理解できました。
では、具体的にどういった場合に、この特例を利用して節税につなげられるのでしょうか。
短期前払費用の特例をどう利用したら節税になるの?
具体例としては、以下のようなケースです。
利益がでている年の12月に、駆け込みで1年前払いのレンタルサーバーを借りる。
これが1年で12万円だとしたら11万円は本来翌年度以降の費用であるはずですが、今年度に費用にすることができ、11万円の所得分が節税になったといえます。
【税務調査対策】短期前払費用の特例で税務署がチェックするポイント
利益がでているから年末に短期前払費用をある程度発生させることは悪いことではありません。
ただし明らかに駆け込みで費用を計上していることは、税務調査がきた場合すぐに見抜かれます。
その場合、本当に短期前払費用の要件を満たしているのか?とツッコミが入る可能性があります。
ですので、4つの要件に照らして問題ないのか?そのための証拠書類はそろっているか?を必ず確認しておきましょう。
特に特殊な費用を短期前払費用の特例で利用している場合は、契約書のみならずサービスの実態を表す納品物なども保管しておくと安心です。
格安で確定申告が可能な税理士
ここで、「税務調査がきても安心なように」、「税務調査がくるのを防ぐために」格安で確定申告を依頼できる税理士を紹介したいと思います。
税理士は質で選んだほうが節税に結果的につながるから良いと税理士である筆者は主張したいところですが、
ほとんどの方は税理士を値段で選ばれているのも事実です。
そこで、個人の皆様にできる限り安い税理士サービスを紹介できないかと選んできたサービスがこちらになります。
弊社が調べた限り、このサービスより安く確定申告を依頼できるところはありませんでした。
短期前払費用のことを勉強している方でまだ税理士をつけていない方は、少しくらい費用を払ってでもいいので税理士をつけることをおすすめします。
どれだけ自分で税金のことを勉強していても、多くの方が勘違いして、理解してしまっているという現状を筆者もよく見ています。
そういった勘違いを防ぐとともに、情報収集の手間を大幅に防げるのが税理士に依頼する最大のメリットなのです。
以下の税理士事務所は10万円前後で確定申告代行を依頼できる非常に格安な税理士事務所です。
みんなの会計事務所の確定申告代行
合計の収入が数百万円程度と低い方は、みんなの会計事務所の確定申告代行サービスを利用いただくと安くなる可能性が高いと思います。
ただし、仮想通貨の収入がある方で、海外の取引所を利用している方には対応していませんので注意してください。
よろしければ、お見積りをとってみてください。
おすすめの税理士や税理士の探し方をご紹介
各地域でのおすすめ税理士や税理士の探し方などをご紹介している記事もあります。
よろしければ、参考にしてみてください。
-
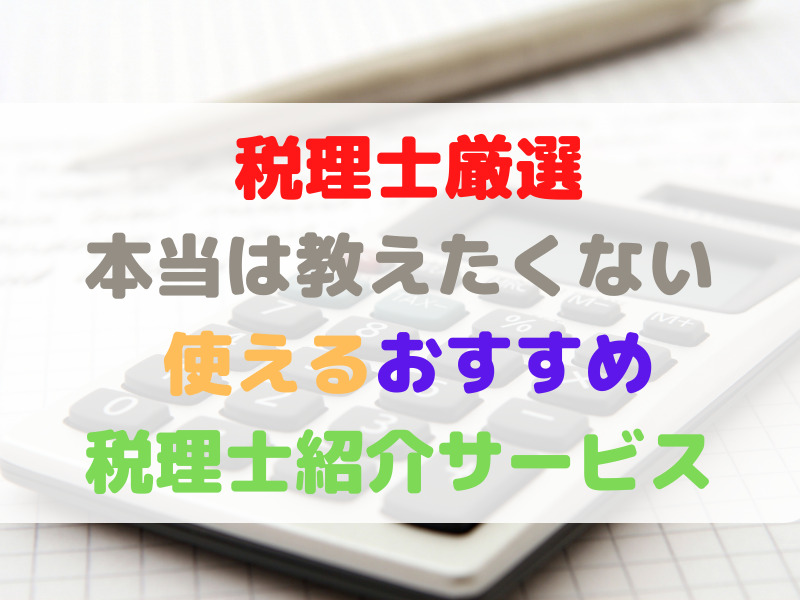
【税理士厳選】評判の良いオススメ税理士紹介サービスランキング8選【相続・個人事業主・中小企業経理担当者必見】
-
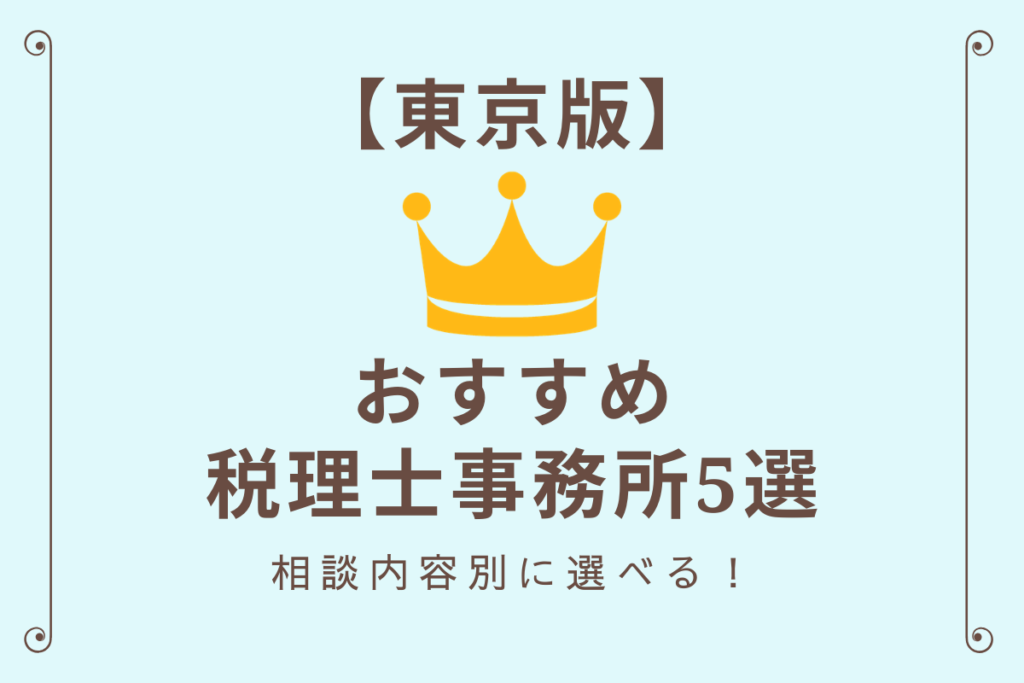
東京でオススメ評判の良い税理士事務所ランキング5選!相談内容(個人・法人・相続)別に解説【一覧から検索、口コミは有効?!】
-
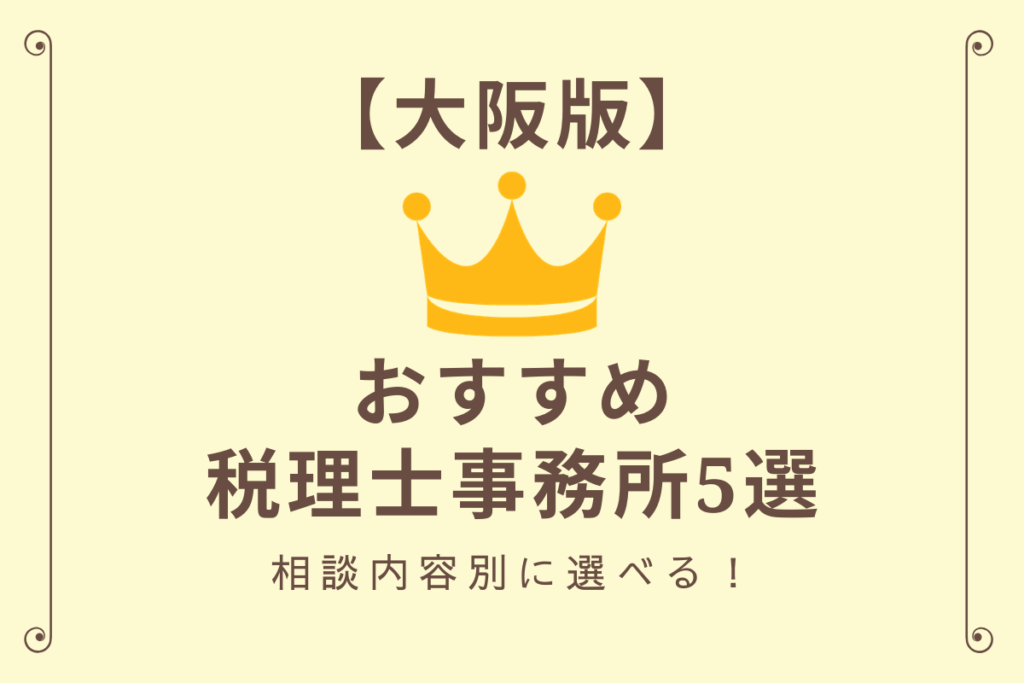
大阪で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続や確定申告・中小企業など相談内容別に比較!
-

【本当は教えたくない】税理士に無料で相談する方法6選【税理士が解説】個人事業主・相続税に悩んでいる方・経理担当者必見!!
-
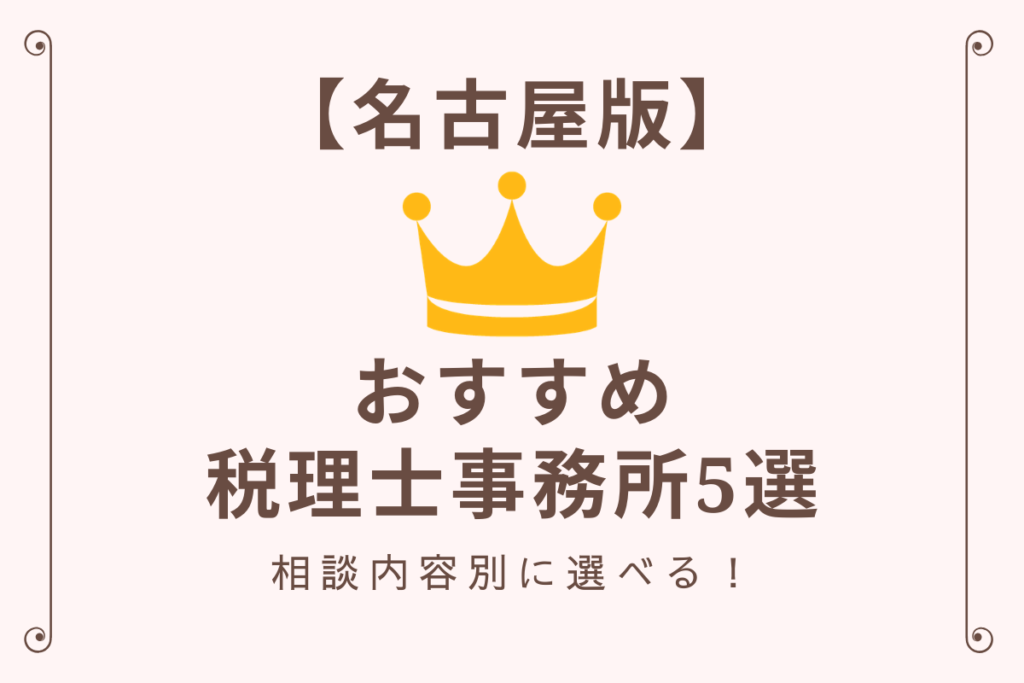
愛知県・名古屋で評判が良い税理士事務所オススメランキング24選!相続や確定申告など相談内容別に解説、比較!
-
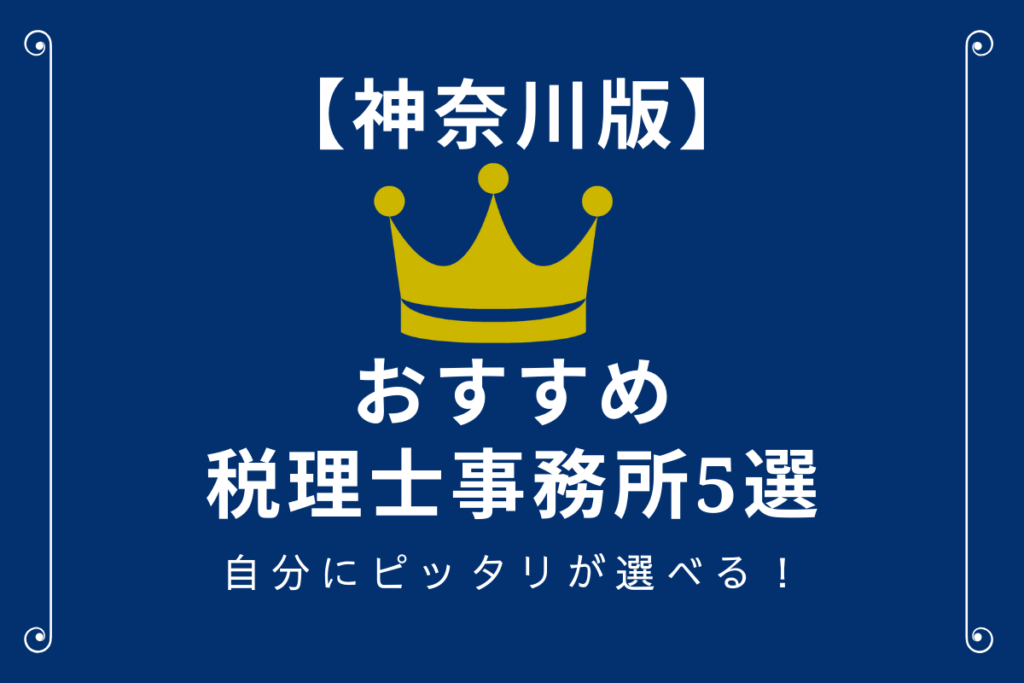
神奈川県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-
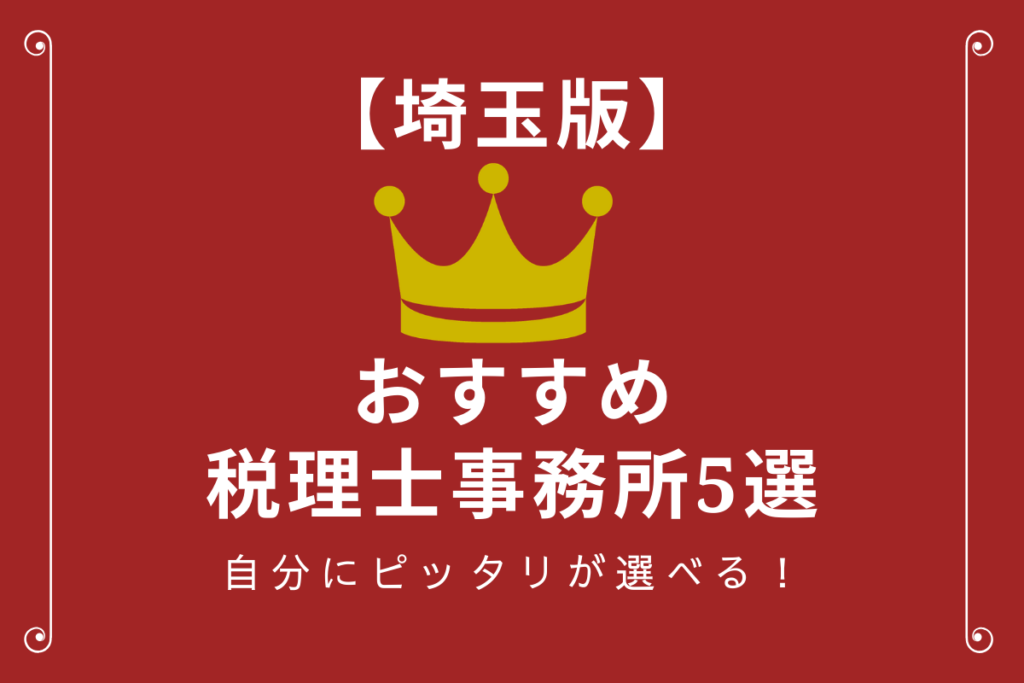
埼玉県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-
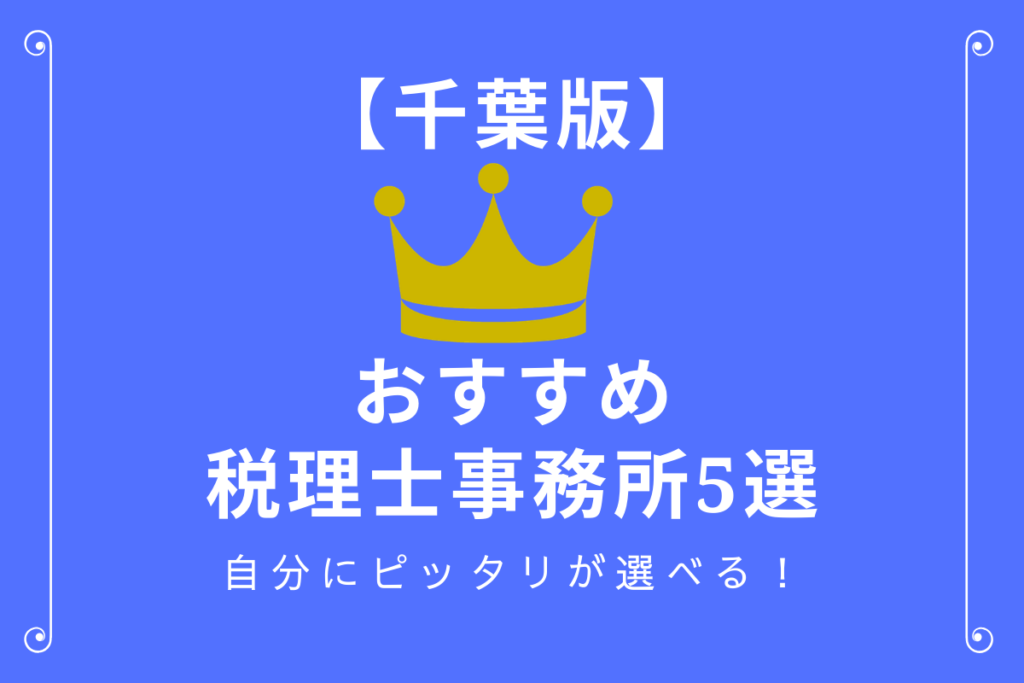
千葉県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

福岡県・福岡市で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相談内容(相続・個人・法人)別に比較、解説【税理士執筆】
-

兵庫県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング15選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

静岡県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

北海道で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

東京都世田谷区で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
短期前払費用の特例は、会計処理を簡単にするために作られた制度
実は、短期前払費用の特例は、会計処理をする実務者を楽にするために考えられた制度なのです。
法人税法の補足として存在する法人税基本通達
法人税の補足として制定された法人税基本通達では、短期前払費用の特例について、2-2-14条において次のように示されています。
参考
「前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」
ここの最後の「認める」というのが実はこの制度の考え方を示しています。
本来前払費用は翌年度に費用になるものです。
短期前払費用の特例はその本来の処理をせずに、特別に支払った日に費用にしてよいといっているのです。
国税庁は、実務の手間削減のために「短期前払費用の特例」を導入
実はこの短期前払費用の特例という制度は、重要性の原則と会計処理の手間を考えた特例なのです。
まず重要性の原則を説明します。
重要性の原則というものが、企業の会計では許されています。
これは重要性が低いものは、実務の手間を考えて、省略してもよいよという企業会計というルールの中にある制度です。
実はこの制度を税務にも取り入れたのが、この短期前払費用の特例なのです。
継続的に発生する短期前払費用を支払った時に費用とすることを認めなかったとしても、2年目以降の費用計上額は実質的に一緒になることから、初年度のみ費用計上の金額がずれるためそもそも重要性は低いといえるのです。
例)7月から1年分を前払で120万円支払っている短期前払費用の処理
①短期前払費用の特例を使った場合
初年度:120万円
2年目以降:120万円
②短期前払費用の特例を使わなかった場合
初年度:60万円(7月から12月の6カ月分)
2年目以降:120万円
重要性が低いわりに、前払費用を毎年管理するのは実は結構手間がかかります。
サービス提供が継続されているが、1年分を前払いにするようなものは保守料など意外にたくさんあります。
このように、本来重要性が低いのに手間がかかるものを、簡単にしてあげるための制度が、短期前払費用の特例なのです。
おすすめのクラウド型会計ソフト3選
さて、そもそも皆さんはどんな会計ソフトを利用していますか。
クラウド型の会計ソフトを使っていない人がもしいれば、経理の工数が相当減ると思いますので、クラウド型会計ソフトを絶対に導入すべきと断言できます。
また、会計ソフト無しで確定申告しようなんて甘い考えをもっている人も、
「安い」クラウド型会計ソフトを導入して経理の時間削減を絶対にすべきです。
会計ソフトのコストよりも、クラウド型会計ソフトを利用することによる、経理時間や経理コストの削減効果の方が大きいからです。
安くて機能も充実しているクラウド型会計ソフトは実は以下の3つしかありません。
| 弥生 オンライン  | マネー フォワード  | freee | |
| 個人 青色申告 | 初年度無料 年11,330円 ※やよいの青色申告 ※初年度無料キャンペーン 利用時翌年度の 年間利用料 【青色申告向け公式HP】 https://www.yayoi-kk.co.jp/…. | 初月無料 年11,880円 ※マネーフォワード 確定申告 ※最も安いプラン 【青色申告向け公式HP】 https://moneyforward.com/…. | 初月無料 年12,936円 ※個人事業主向け ※最も安いプラン 【青色申告向け公式HP】 https://www.freee.co.jp/ |
| 個人 白色申告 | 永久無料 ※やよいの白色申告 【白色申告向け公式HP】 https://www.yayoi-kk.co.jp/…. | 初月無料 年11,880円 ※マネーフォワード確定申告 ※最も安いプラン 【白色申告向け公式HP】 https://moneyforward.com/…. | 初月無料 年12,936円 ※個人事業主向け ※最も安いプラン 【白色申告向け公式HP】 https://www.freee.co.jp/ |
| 法人 | 初年度無料 年30,580円 【法人向け公式HP】 https://www.yayoi-kk.co.jp/…. | 初月無料 年39,336円 ※最も安いプラン 【法人向け公式HP】 https://moneyforward.com/…. | 初月無料 年39,336円 ※2024年7月以降 ※最も安いプラン 【法人向け公式HP】 https://www.freee.co.jp/ |
| 使いやすさ | 経験者向け | 経験者向け | 初心者向け |
| 機能面 | 機能充実 | 機能充実 | 機能充実 |
個人的には会計初心者であれば、一番安いかつ初年度無料のやよいオンラインを使っておくのが良いでしょう。
慣れてきたら色々な会計ソフトを試してみて使いやすいソフトに乗り換えていくのも手です。
ちなみに、おすすめの会計ソフトの紹介記事もありますので、よろしければご覧ください。

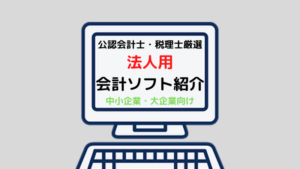
まとめ
短期前払費用の特例を活用すれば、毎月の支払の手間も減り、今期の費用として節税対策となります。
短期前払費用を正しく理解して、節税に役立てましょう。