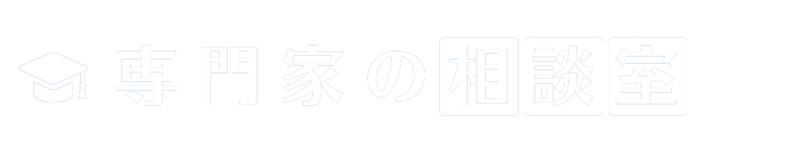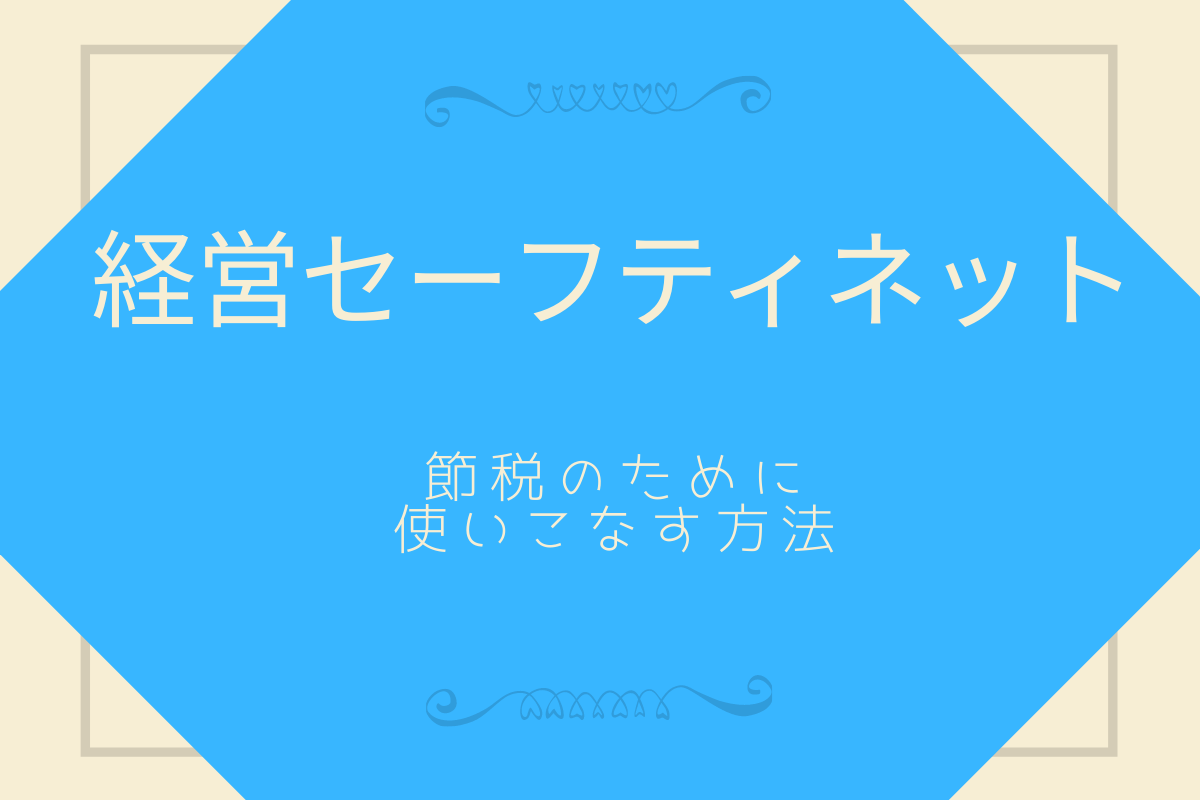みなさんは「経営セーフティ共済」という制度をご存知でしょうか。
個人事業主になったばかりの人にはなじみのない制度かもしれませんが、実は節税を考える上ではぜひ覚えておきたい制度です。
そうした経営セーフティ共済のメリット、デメリットはずばり以下のようになります。
▼この記事でわかること
【メリット①】
経営セーフティ共済は得意先や取引先が倒産したらすぐに融資が受けられる
【メリット②】
経営セーフティ共済は掛金を全額経費にでき、一定期間経った後解約すれば全額掛金が戻ってくる
【デメリット】
経営セーフティ共済は解約時受け取る掛金の戻りは収入になってしまう
以下、この点について詳しく解説していますので参考にしてみてください。
経営セーフティ共済は、得意先や取引先が倒産したときに備えるセーフティネット
ずばり、経営セーフティ共済は得意先や取引先などの倒産に備えることができる共済であり、個人事業者だけではなく、中小法人など幅広い事業者にとってメリットがある共済です。
中小法人が連鎖倒産するのを防ぐ目的でつくられた制度
これから個人事業主として事業を行っていくにあたっては、様々なリスクを背負っていかなければいけません。
そのリスクの中でも大きなリスクといえるのが「倒産リスク」です。
ビジネスの基本は「サービスの提供や商品の販売を行い、相手先から代金をもらう」ということです。
しかし、相手先が様々な事情により倒産してしまった際はどうなるでしょうか。
相手先が倒産してしまうと、その時の売上代金を回収することは困難になります。
そのため、結果として損をしてしまい、最悪の場合、自分自身も倒産の危機に立たされる可能性もあります。
このように相手先が倒産することで、自分たちが連鎖的に倒産することを防ぐためにつくられた制度が「経営セーフティ共済」です。
最大のメリットは得意先、取引先が倒産後すぐに融資が受けられる点!
経営セーフティ共済の一番のメリットともいえるのが融資の面です。
相手先が倒産し売上代金などを回収できなくなった場合には資金が不足してしまいます。
そのような場合には「共済金の貸し付け」というかたちで融資を受けることができます。
相手先の倒産が確認されるとすぐに受け取ることができるため、事業者にとって非常に心強い制度といえます。
ただし、あくまでも倒産したことが確認できた場合に受けることができるため、夜逃げなど倒産の事実が確認することができない場合は、この共済金貸付制度を適用することはできません。
相手先が倒産していない場合には「一時貸付金」として事業資金の融資を受けることは可能です。
融資の上限は、無担保・無保証人で掛け金の10倍となっている点も非常にお得!
融資を受けることができる金額については前提条件として下記の条件を満たしていなければいけません。
経営セーフティ共済の融資ポイント
- 加入後6ヶ月を経過していること
- 6ヶ月分以上の掛金を既に支払っていること
この2つの要件を満たすことで「無担保」「無保証人」で融資を受けることができます。
また融資の上限金額についても、
融資金額の上限
- 既に支払っている掛金総額の10倍(掛けることができる金額は800万円が限度額)
- 相手先の倒産によって生じる被害額
このどちらか少ない方の金額の範囲内で8,000万円を限度額とされています。
40か月以上掛金を納めていれば、解約しても掛金全額が戻る!
経営セーフティ共済を解約する場合、解約返戻金を受け取ることができる点も非常に魅力的な点の一つです。
ただし、注意が必要なことがあります。それは掛金をどれくらいの期間支払っていたかです。
掛金の支払期間が40ヶ月以上であれば、既に支払った掛金が100%返金されますが、40ヶ月未満であれば100%返金されず「元本割れ」ということになってしまいます。
解約返戻金については申請書類を提出することで比較的短期間で受け取ることができますが、再び経営セーフティ共済に加入する場合には解約から1年間待つ必要があります。
注意ポイント
・40か月以上⇒掛け金が100%返金
・40か月未満⇒元本割れ
掛金全額を法人の場合は損金に、個人事業主の場合は必要経費に算入できるため節税効果抜群!
経営セーフティ共済での掛金はすべて経費(損金・必要経費)として処理することができます。
経費として処理することができれば、「売上」から「経費」を差し引いた「所得」を減らすことにつながります。
「所得が下がる」=「税金が下がる」
ということですので、経営セーフティ共済は万が一に備えながら、高い節税効果を得ることもできることから、事業者にとっては非常に魅力的な制度であるといえます。
ただし、経費として処理するには申告の際に所定の添付書類をつける必要があるので忘れないように注意しましょう。
掛金を毎月変更できる点も魅力の一つ!ただし減額時は注意!
経営セーフティ共済には「掛金を自由に設定できる」という大きなメリットもあります。
掛金は月額5千円から20万円の範囲で自由に行うことができ、5千円単位で細かく設定することができます。
ただし、掛金を減額する場合には次の条件のいずれかに該当する場合のみです。
減額の条件
- 事業規模の縮小による
- 経営の著しい悪化などの一定の理由により払い込みが困難な場合
- 借入金の貸付残高と支払った掛金総額の10倍した額の合計が8千万に達する場合
掛け金の金額設定はよく考えて行う必要がありますね。
1年以内の前納掛金も必要経費に算入できる
経営セーフティ共済の場合、翌年1年分の掛金をまとめて前納することもできます。
前納した掛金も支払った日の事業年度の経費として処理することができます。
それにより、当期分と翌期分の2期分をまとめて経費として処理することができ、高い節税効果を得ることができます。
前納掛金に対してキャッシュバックを受けられる
翌期分の掛金を前納した場合には「前納減額金」という割戻金のようなかたちでキャッシュバックを受けることができます。
前納減額金の計算式は次のとおりです。
【前納減額金】 = 1ヶ月あたりの掛金 × 0.9 × 1,000 × これまで支払った掛金の累計月数
また、この場合の注意事項として次のことが挙げられます。
注意ポイント
・12ヶ月を越える分の掛金を前納する場合には掛金の月数は12ヶ月としてカウントされる
・受け取った前納減額金は申告の際には事業所得として収入に計上しなければならない
前納をうまく利用して、年末に翌年1年分の掛金を一括払い込みすることで、利益コントロールに使える
経営セーフティ共済の掛金についての特徴として、前納した掛金も支払った年度の経費に入れることができるとご紹介しました。
ということは2年分の掛金を一度に経費とすることが可能ということになります。
そのため、1年間で経費とすることができる限度額は下の①と②の合計で480万円となります。
- 20万円/月 ×12ヶ月 = 240万円 (今年分の掛金)
- 20万円/月 ×12ヶ月 = 240万円 (翌年分の掛金)
利益が多く出ている年においては、この前納制度で480万円という大きな経費をつくることで利益を減らし、最終的な税金を少なくすることができます。
経営セーフティ共済を利用するにあたっての注意点は?
経営セーフティ共済は上記のように非常に魅力的な制度といえますが、注意しなければならない点もいくつかあります。
これらの注意点を把握した上で加入した方がよいのかどうかを判断していきましょう。
解約手当金は収益計上となる
「経営セーフティ共済を解約した場合には解約返戻金を受け取ることができる」ということを前述しましたが、解約返戻金を受け取った際は「収入」として申告しなければなりません。
そのため利益が多く出ている年などに解約してしまうと、思いがけない金額の税金が発生する場合があり、解約する際のタイミングが非常に重要になってきます。
借入は実質的には無利子ではない
経営セーフティ共済での共済金借入に関しては「無利子」となっています。
しかし借入を受けた際には、その借入金額の10%相当額が支払った掛金から控除されてしまいます。
つまり、控除された額について、掛金における権利が消滅してしまうということです。
これはどういうことかというと、例えば2,000万円の共済金貸付を受けた場合、2,000万円の10%相当額である200万円相当の掛金の権利が消滅することになるので、実質的には2,000万円を借り入れて、200万円の利息を支払っていることと同じことになってしまいます。
早期解約すると元本割れもしくは掛捨てになる
経営セーフティ共済については解約時に返戻金が発生し、その金額はこれまで支払ってきた掛金分に相当しますが、これは40ヶ月以上の支払い実績がある場合だけです。
支払い実績が40ヶ月に満たない場合は支払った掛金分すべては返ってこず、「元本割れ」となってしまいます。
さらに、支払い実績が1年未満の場合の返戻率は0%となるため、1円も返ってこないということになります。
起業1年目では加入できない
経営セーフティ共済に加入するには大前提の条件として、
「事業を継続して1年以上おこなっている」
という条件があります。
そのため、起業して1年に満たない事業者に関しては加入要件を満たしていないということになり、経営セーフティ共済に加入することはできません。
事業所得以外の収入には掛金の必要経費は認められない
経営セーフティ共済においては支払った掛金は経費になると前述しましたが、注意事項として個人事業の種類のうち、不動産所得などの事業所得以外の業種の場合は支払った掛金を経費とすることはできません。
経営セーフティ共済の加入手続きは?
経営セーフティ共済へ加入するには、準備する書類などが法人と個人とで少し異なります。
今回は個人事業主の場合における加入手続きの流れや必要書類についてご紹介していきます。
ステップ①必要書類を入手、作成
経営セーフティ共済へ加入するには、まず以下の書類を準備する必要があります。
加入に必要な書類
- 確定申告書
- 青色申告決算書・白色申告決算書・収支内訳書等
- 所得税の納税証明
- 確定申告書を作成するにあたり使用した帳簿など
ステップ②窓口へ提出
準備した資料と、作成した書類を窓口へ提出します。
加入窓口については以下のとおりです。
加入窓口
- 中小機構が委託した団体
- 融資取引がある金融機関
- 1年以上の預金取引のある金融機関
ただし、3の「1年以上預金取引のある金融機関」を加入窓口とする場合には、必要な書類や手続きが異なる場合もあるので注意が必要です。
ステップ③書類の受け取り
窓口へ必要書類を提出後、中小機構から「共済契約締結証書」「加入者必携」が送付されてきます。
これらの書類は重要書類となるので、無くさないように大切に保管しておきましょう。
経営セーフティ共済に加入できないケースがある?!
経営セーフティ共済に加入するには前述のとおり、事業を継続して1年以上おこなっているということが大前提となります。
この条件を満たしたうえで、さらに業種や資本金、従業員の数など下記の要件を満たすことが必要になります。
| 業 種 | 出資総額 | 常時雇用の従業員数 |
| 製造業
建設業 運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以上 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以上 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以上 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以上 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以上 |
| ソフトウェア業
情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以上 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以上 |
副業しているサラリーマンでも経営セーフティ共済は使える?!
経営セーフティ共済は事業者のみを対象としているため、副業のあるサラリーマンなどは加入することはできません。
しかし副業が事業規模と判断されれば加入できる可能性はあります。
加入できるかどうか、わからない場合は一度窓口に問い合わせてみましょう。
不明点があれば、中小企業基盤整備機構の窓口に問い合わせしましょう
経営セーフティ共済を加入するにあたっては、制度の概要や加入要件、加入手続きなど不明な点などは多くあるかと思います。
手続きなどに不備があると訂正による手間や時間を多くかけてしまうことになるため、少しでも不明なところがある場合には中小企業基盤整備機構の窓口に問い合わせるようにしましょう。
参考
■中小企業基盤整備機構の窓口
経営セーフティ共済を使った高度な節税術を大公開
経営セーフティ共済の節税メリットなどは先ほど紹介しましたが、実際にどのように使うとよいのかをここからは説明していきます。
所得の平準化を図るように掛金を前後させる
日本の所得税制は、累進課税が採用されているため、利益が出れば出るほど税率が上がってきます。
そのため、売上から経費や各種控除(生命保険控除や扶養控除など)を差し引いた課税所得にばらつきがある場合と、課税所得が平準化されている場合とでは税負担が大きく異なります。
(例1)課税所得にばらつきがある場合
| 課税所得 | 税率(復興税除く) | 税 額 | |
| 1年目 | 100万円 | 5% | 5万円 |
| 2年目 | 400万円 | 20% | 37.25万円 |
| 3年目 | 70万円 | 5% | 3.5万円 |
| 合計 | 570万円 | ― | 45.75万円 |
(例2)課税所得が平準化されている場合
| 課税所得 | 税率(復興税除く) | 税 額 | |
| 1年目 | 190万円 | 5% | 9.5万円 |
| 2年目 | 190万円 | 5% | 9.5万円 |
| 3年目 | 190万円 | 5% | 9.5万円 |
| 合計 | 570万円 | ― | 28.5万円 |
上記の表を見てわかるように、3年間の合計では同じ課税所得金額にもかかわらず、納税額の合計は約17万円も差額が生じてしまいます。
そのため、経営セーフティ共済の通常の掛金や前納制度などをタイミングよく活用することで所得を平準化することでき、節税効果を高めることができます。
赤字が出るタイミングで解約する
経営セーフティ共済を解約する際に受け取る金額はすべて「収入」になるため、解約するタイミングが大事ということは上記にて前述しましたが、具体的なタイミングとはいつなのでしょうか。
解約するタイミングとしては以下のような場合がベストといえます。
【1】赤字が出そうな年
上記の所得の平準化と同様で大きな利益が出ている年に解約してしまうと、事業収入に解約返戻金がさらに加算されるため、課税所得が膨らみ税率が上がってしまいます。
そのため解約する際には赤字が出そうな年におこなうことで、赤字部分と解約返戻金が相殺され、最低限の所得に抑えることができます。
(例1)黒字の時に解約する場合(解約金:500万円の場合)
| 課税所得 | 税率(復興税除く) | 税 額 | |
| 1年目 | 600万円 (100万円 + 500万円) | 20% | 77.25万円 |
| 2年目 | ▲400万円 | 0% | 0万円 |
| 3年目 | 70万円 | 0% | 0万円 |
| 合計 | 270万円 | ― | 77.25万円 |
(例2)赤字の時に解約する場合(解約金:500万円の場合)
| 課税所得 | 税率(復興税除く) | 税 額 | |
| 1年目 | 100万円 | 5% | 5万円 |
| 2年目 | 100万円 (▲400万円 + 500万円) | 5% | 5万円 |
| 3年目 | 70万円 | 5% | 5万円 |
| 合計 | 270万円 | ― | 15万円 |
このように解約するタイミングによっては税率が高くなってしまうことから、解約するタイミングがいかに重要であるかがよくわかるかと思います。
解約するタイミングはその他にも下記のようなタイミングも節税効果が高いといえます。
【2】赤字の繰越が失効する年
所得税の申告時において赤字が発生した場合には、その赤字は3年間繰り越すことができます。
繰り越した赤字は翌年以降の黒字と相殺することができますが、黒字が出ないまま3年を経過してしまうと、その赤字の繰り越しは失効してしまいます。
この赤字の繰り越しが失効する年に解約することで解約返戻金と赤字の繰り越しを相殺させることができるため、最低限の所得に抑えることができます。
法人に比べて個人事業主は節税効果が薄いといわれている
個人事業主でも十分節税に役立てることはできますが、実はちまたでは法人の方が節税に役立てられるという意見もききます。
その理由をご説明します。
所得税は累進課税である一方で法人税は税率が一定
個人の所得税は累進課税となり税率が5%~45%の幅で変動しますが、法人では一定の所得金額を超えない限りは税率が15%~25%程度と一定となっています。
そのため、利益が出ている場合では累進課税の方が所得を平準化することができ節税につなげることができますが、利益が少ない場合は税率が5%や10%となり、節税効果をあまり得ることができません。
その点に関しては一定税率の法人のほうが所得の調整が行いやすいといえます。
個人事業主の場合、所得を赤字にしにくい
法人の場合は、社長などの役員へ給与を支払うことで大きな経費をつくることができます。
これは「赤字をつくりやすい」と言い換えることもでき、そのタイミングに合わせて解約することにより高い節税効果を得ることができますが、個人事業主の場合は自分自身への給与は経費にすることができないため、意図的な赤字を作りづらいとえいます。
役員の退職金と相殺させることができない
法人の場合は、役員への給与以外にも退職金も経費にすることができます。
そのため役員への退職金を支給し、大きな赤字を作ることができます。
その時の赤字と解約返戻金を相殺させることにより高い節税効果を得ることができますが、個人事業主の場合は自分自身への退職金を経費にすることはできません。
様々なブログで紹介されていますが、結局、節税に役立たせるかどうかは自分次第!
個人事業主の場合は経営セーフティ共済の他にも「小規模企業共済」や「iDeCo」などの制度を活用することで高い節税効果を得ることもできます。
これらについても個人事業主としては知っておいて損はない制度ですので、経営セーフティ共済と併せて覚えておきましょう。
ちなみにiDeCoについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご一読ください。

格安で確定申告が可能な税理士
最後に、格安で確定申告を依頼できる税理士を紹介したいと思います。
税理士は質で選んだほうが節税に結果的につながるから良いと税理士である筆者は主張したいところですが、
ほとんどの方は税理士を値段で選ばれているのも事実です。
そこで、個人の皆様にできる限り安い税理士サービスを紹介できないかと選んできたサービスがこちらになります。
弊社が調べた限り、このサービスより安く確定申告を依頼できるところはありませんでした。
節税のことを勉強している方でまだ税理士をつけていない方は、少しくらい費用を払ってでもいいので税理士をつけることをおすすめします。
どれだけ自分で税金のことを勉強していても、多くの方が勘違いして、理解してしまっているという現状を筆者もよく見ています。
そういった勘違いを防ぐとともに、情報収集の手間を大幅に防げるのが税理士に依頼する最大のメリットなのです。
以下の税理士事務所は10万円前後で確定申告代行を依頼できる非常に格安な税理士事務所です。
みんなの会計事務所の確定申告代行

合計の収入が数百万円程度と低い方は、みんなの会計事務所の確定申告代行サービスを利用いただくと安くなる可能性が高いと思います。
ただし、仮想通貨の収入がある方で、海外の取引所を利用している方には対応していませんので注意してください。
よろしければ、お見積りをとってみてください。
税理士の探し方や各地域でのおすすめ税理士をご紹介
各地域でのおすすめ税理士や税理士の探し方などをご紹介している記事もあります。
よろしければ、参考にしてみてください。
-
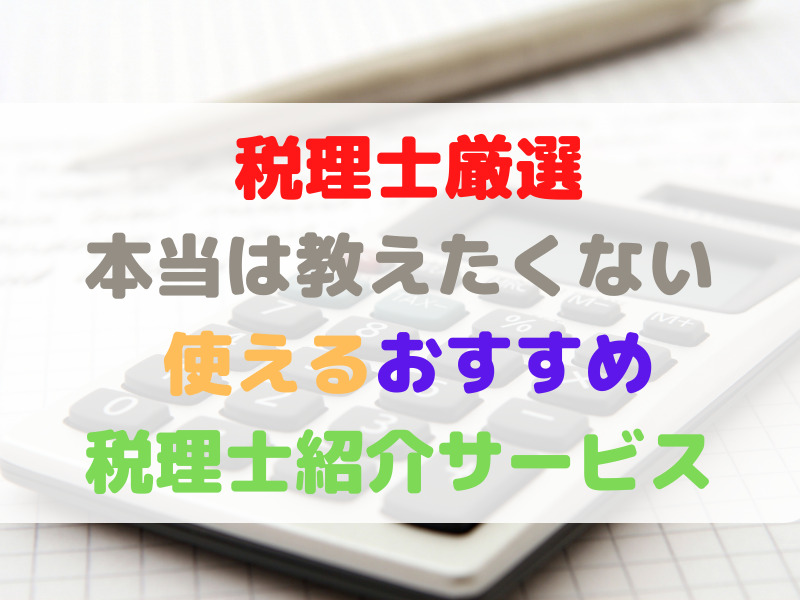
【税理士厳選】評判の良いオススメ税理士紹介サービスランキング8選【相続・個人事業主・中小企業経理担当者必見】
-
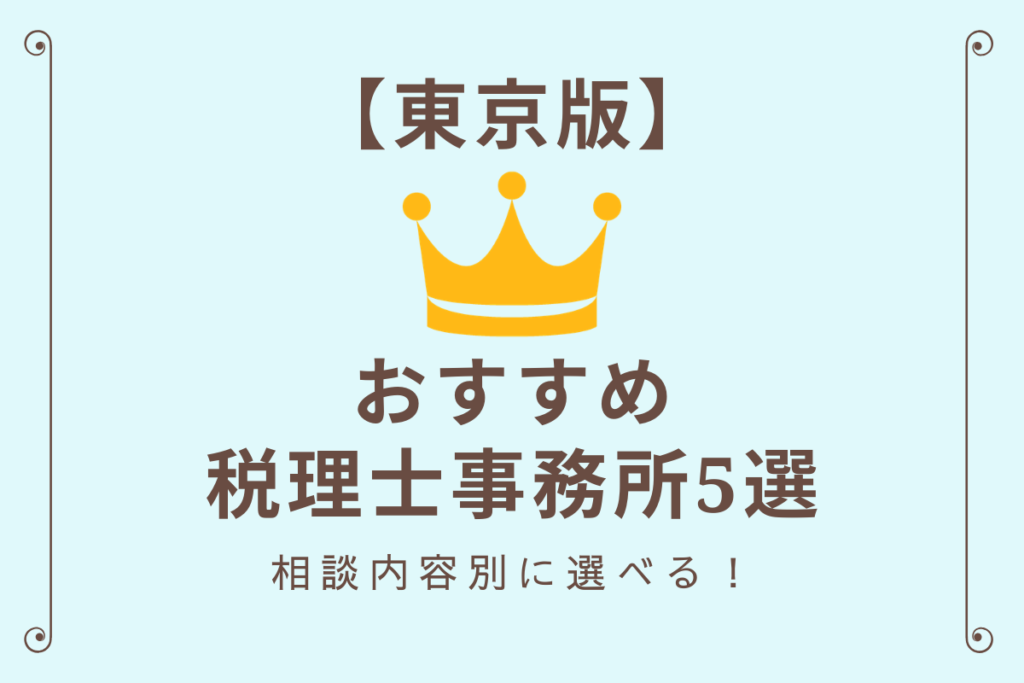
東京でオススメ評判の良い税理士事務所ランキング5選!相談内容(個人・法人・相続)別に解説【一覧から検索、口コミは有効?!】
-
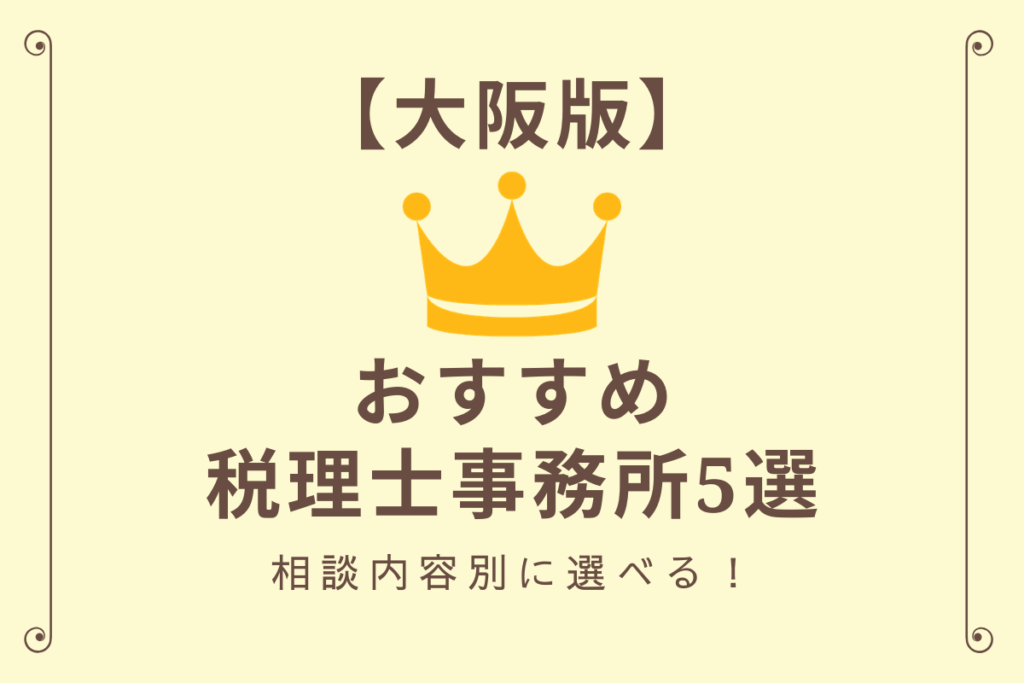
大阪で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続や確定申告・中小企業など相談内容別に比較!
-

【本当は教えたくない】税理士に無料で相談する方法6選【税理士が解説】個人事業主・相続税に悩んでいる方・経理担当者必見!!
-
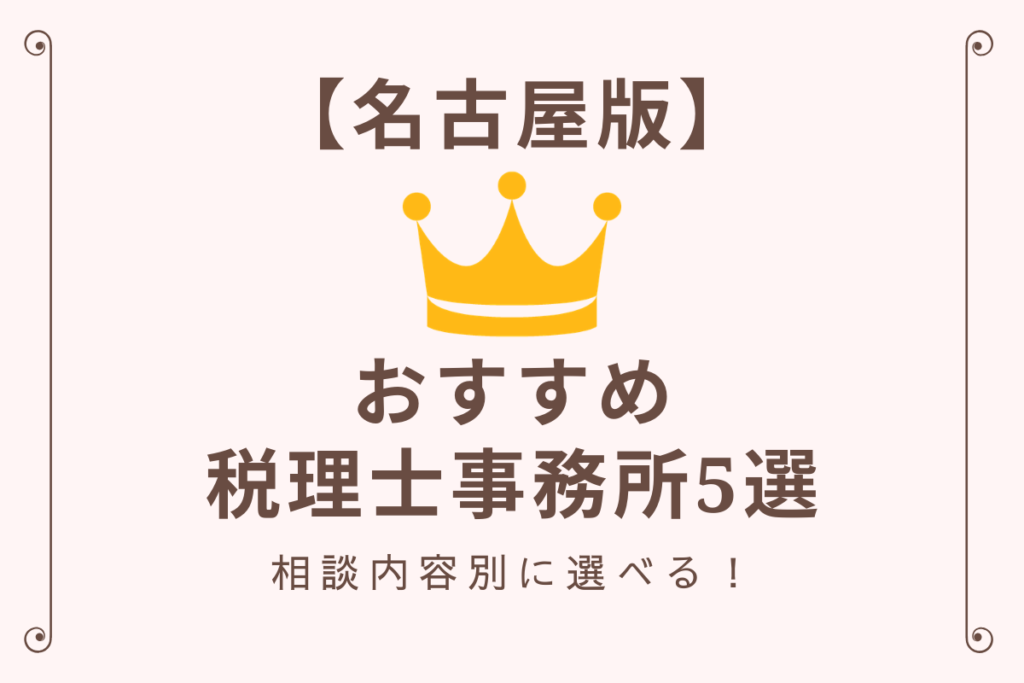
愛知県・名古屋で評判が良い税理士事務所オススメランキング24選!相続や確定申告など相談内容別に解説、比較!
-
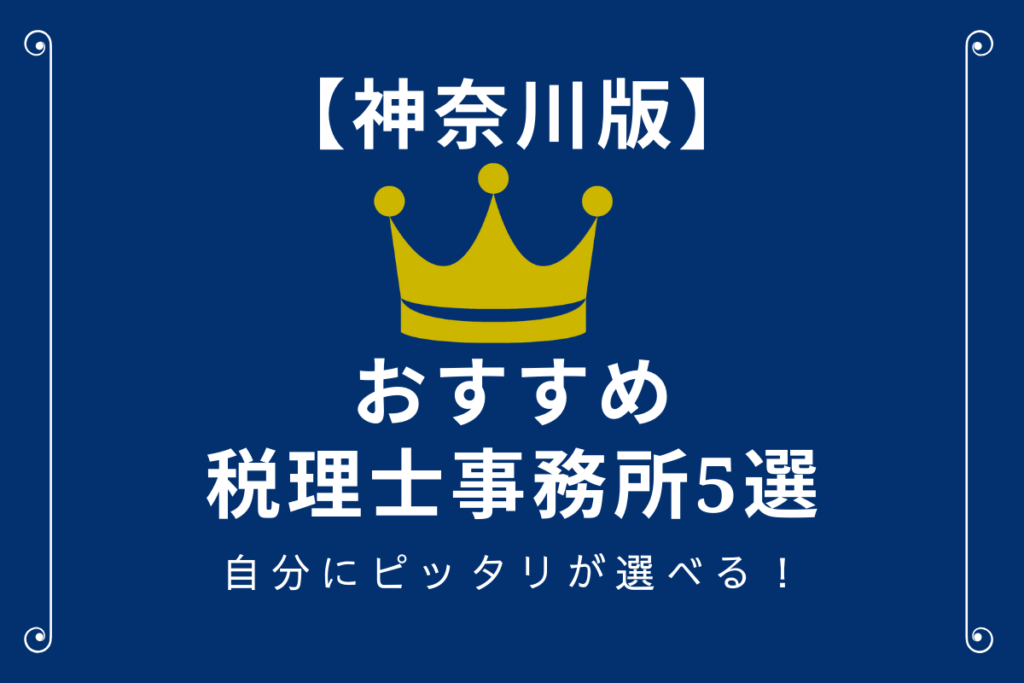
神奈川県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-
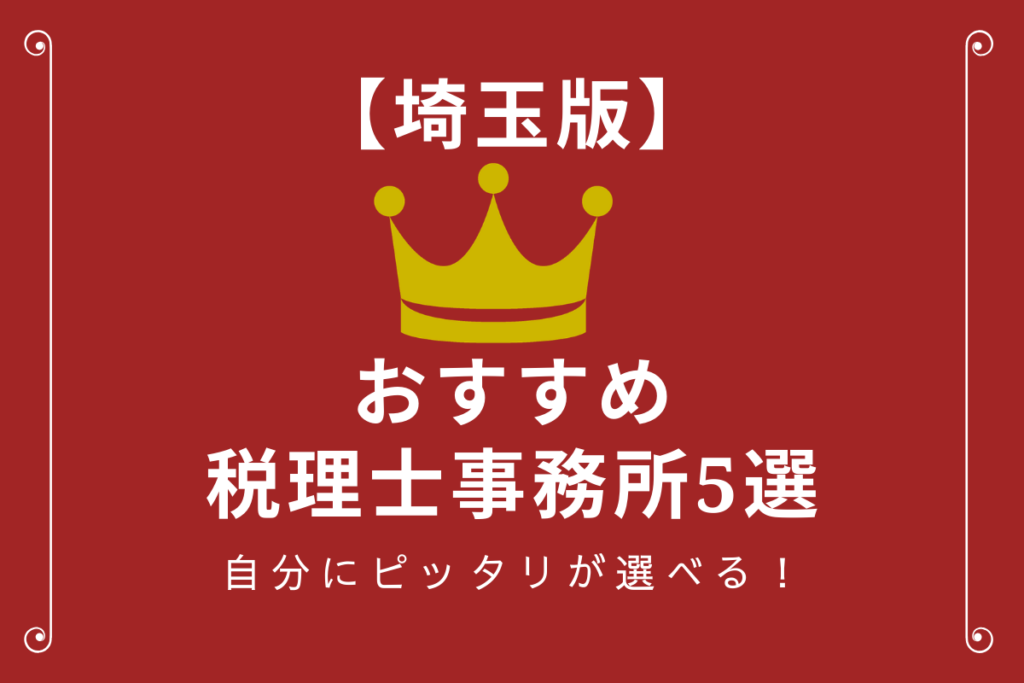
埼玉県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-
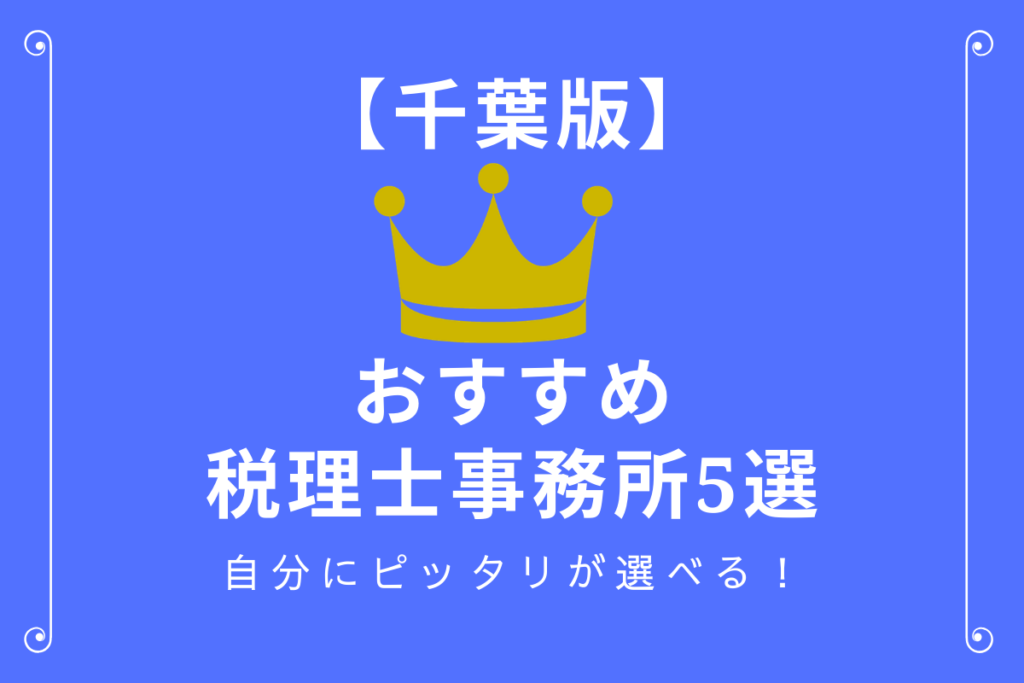
千葉県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

福岡県・福岡市で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相談内容(相続・個人・法人)別に比較、解説【税理士執筆】
-

兵庫県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング15選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

静岡県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

北海道で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

東京都世田谷区で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
掛金支払時、解約時の経理処理を解説
経営セーフティ共済の経理処理をまとめると下記のようになります。
■掛金を支払った場合(月払・年払・前納)
| 借方 | 金 額 | 貸方 | 金 額 |
| 保険料 | ×××× | 現金・預金 | ×××× |
■解約返戻金を受け取った場合
| 借方 | 金 額 | 貸方 | 金 額 |
| 現金・預金 | ×××× | 雑収入 | ×××× |
おすすめのクラウド型会計ソフト3選
さて、そもそも皆さんは今現在どんな会計ソフトを利用していますか。
クラウド型の会計ソフトを使っていない人がもしいれば、経理の工数が相当減ると思いますので、クラウド型会計ソフトを絶対に導入すべきと断言できます。
また、会計ソフト無しで確定申告しようなんて甘い考えをもっている人も、
「安い」もしくは「無料の」クラウド型会計ソフトを導入して経理の時間削減を絶対にすべきです。
会計ソフトのコストよりも、クラウド型会計ソフトを利用することによる、経理時間や経理コストの削減効果の方が大きいからです。
「安い」もしくは「初年度無料」で機能も充実しているクラウド型会計ソフトは実は3つしかありません。
おすすめの会計ソフト
・freee・・・初心者向け/年間11,760円(税抜)/初月無料
・マネーフォワード・・・経験者向け/年間10,800円(税抜)/初月無料
・やよいオンライン・・・経験者向け/年間8,800円(税抜)/初年度無料
ちなみに、おすすめの会計ソフト、会計アプリの紹介記事もありますので、よろしければご覧ください。


まとめ
経営セーフティ共済は取引先が倒産したときに備えることを目的としている共済です。
その一方で、利益を調整することで高い節税効果を得ることができる共済制度でもあります。上
記のように経営セーフティ共済にはメリットやデメリットがありますので、それぞれをしっかりと把握した上で節税に役立てていきましょう。