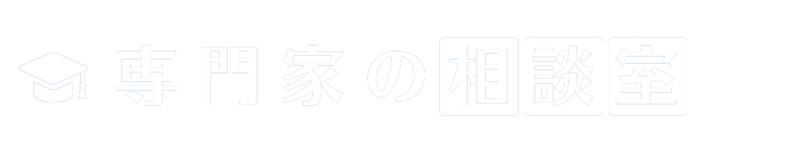車を仕事で利用しているのに、車関連の経費を計上できていない個人事業主の方は意外と多いのではないでしょうか?
車関連の経費を計上すれば、大きな節税に期待できるかもしれません。
今回は車関連の経費を使ったおすすめの節税術を大公開します。
▼この記事でわかること
・車の購入代金は減価償却費を通して毎月一定割合を経費にできる
・高級外車であっても経費にすることは可能
・プライベート・事業兼用の車も家事按分を使って経費にできる
節税にかかわる車関連経費はガソリン代から車検代、備品に至るまで多岐にわたる!
まず、車関連の費用で経費にできるものを以下に洗い出してみました。
基本的には車を事業用のみに使っていれば、これらの費用すべてを経費にすることができます。
また車を事業用とプライベート用の両用で使っている場合も、これらの費用の一部割合を経費にすることができます。
▼車に関する費用で経費にできるもの一覧
| 勘定科目 | 内容 |
| 租税公課 | 自動車税、自動車取得税、自動車重量税 |
| 保険料 | 自賠責保険、任意保険、車両保険 |
| 車両費 | ガソリン代、洗車代、点検費用、車検費 |
| 減価償却費 | 車購入代金を数年間で按分し費用計上したもの |
| 旅費交通費 | 高速代金、ETC代、駐車場代 |
| 賃借料 | 駐車場代 |
| 消耗品費 | タイヤ、オイル、携帯フォルダーなどの備品 |
| 支払利息 | 車購入のためのローンの支払金利 |
車の購入代金そのものやローンの元金支払そのものを経費にすることはできない!
車の購入代金支払いやローンの元本支払は一つ一つの支払いが多額になりますが、この支払そのものを経費に計上することはできないので注意してください。
また、車の購入代金の中には、購入時にオプションとしてつけたカーナビ代などの付属品も含まれる点に注意が必要です。
一方で、保険料などは同時に支払ったとしても、取得費用に含めず、支払い時点で全額を経費にすることができます。
なお、何を付随費用に含めなくてよいのかについては、以下の国税庁HPを参考にするとよいでしょう。
車の購入代金は支払い時点では資産計上し、その後減価償却費として、耐用年数とよばれる資産の寿命のようなものを利用して、一定額ずつに按分し、毎月計上することになります。
車購入時に頭金を払った場合にも、一度前払金として処理し、実際に車が届いてから、前払金と残額を合わせて、減価償却費として経費計上していきます。
また、車購入のために組んだローンの元本支払いは費用計上できません。
これは、借りた際に負債とし、それを期間ごとに一定ずつ返済し取り崩すだけのものであり、費用計上する性質のものではないからです。
中古車を購入した方が得になる?減価償却費の計算方法から仕訳まで徹底解説
中古車を購入した場合、耐用年数が下がることがあり、結果的に1年間の減価償却費をより多く計上することができる可能性があります。
例えば、経過年数が相当程度たっているにもかかわらず、新品と同じような状態の中古車を買った場合には、中古車を購入した方が、節税効果が高いと言えるかもしれません。
さて、ここで改めて車を購入した際の減価償却費の考え方を解説します。
まず、減価償却費には定額法と定率法があります。
届出を出さなければ原則として定額法となり、法定耐用年数が経過するまで、毎月定額を減価償却費として計上します。
ただし、届出を出せば、定率法という取得1年目の減価償却費が多額に計上でき、その後徐々に減価償却費が下がっていくような計上方法も認められているため、減価償却費が多く発生するような場合には、事前に届出をすることも考えてみましょう。
参考
ここまでのポイント
- 定額法⇒毎月定額を計上。基本はこちらになる
- 定率法⇒1年目に多額を計上できる。ただし届け出が必要
次に、耐用年数ですが、新品購入の場合の耐用年数は、軽自動車で4年、一般的な乗用車で6年となっています。
参考
一方で中古資産の場合だと、一般的な乗用車は耐用年数が経過したものであれば最低年数である2年間、耐用年数が一部経過している場合はその経過年数×20%+残りの年数となります。
ただし端数が出た場合は切り捨てになります。
参考
▼一般車の耐用年数のまとめ
| 種別 | 耐用年数 | |
| 新車 | 軽自動車 | 4年 |
| 新車 | 一般車 | 6年 |
| 中古車 | 耐用年数が経過した車 | 2年 |
| 中古車 | 耐用年数が残っている車 | 経過年数×20%+残りの耐用年数 |
具体的に、営業用に利用する中古(経過年数2年)の乗用車を10月に240万円で購入したとしましょう。
購入時の仕分けはこうなります。
購入時の仕分け
車両 240万円 / 現金預金 240万円
さて、次に毎月の減価償却費を計算します。
耐用年数は、以下のような計算で算出します。
2年(経過年数)×20%+(6年(法定耐用年数)―2年(経過年数))=4.4年⇒(端数切り捨てで)4年
したがって、毎月の減価償却費は、
毎月の減価償却費
240万円÷4年÷12か月=5万円
となります。
したがって毎月の減価償却費の仕訳は以下のようになります。
毎月の減価償却費の仕分け
減価償却費 5万円 / 車両 5万円
先ほど、定率法の届出を出せば、取得年度に多くの経費計上ができることはお伝えしました。
しかしながら実は定率法の場合、耐用年数が2年であれば、初年度に全額を経費計上することができます。
これを利用すれば、例えば、耐用年数が2年となるように型落ちの中古車を購入することで、実は購入代金全額を初年度に経費計上するという裏技が存在します。
「4年落ちのベンツを買え」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
実は、4年経過のベンツの中古車は、耐用年数が2年になり、かつベンツなので一定高額であることから、節税目的に使いやすいのです。
フェラーリやポルシェ、ランボルギーニなどの超高級外車も経費になるか?
面白い話として、フェラーリやランボルギーニ、ポルシェなどの超高級外車は経費に認められないのではないかという話があります。
結論として昔は認められないとされていましたが、今は過去の判例でも高級外車でも経費に認められているようですので、基本的には車種は気にしなくてよいでしょう。
もちろん先ほど例にふれたベンツやBMW、ジャガーなども同様です。
また減価償却についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をあわせてご覧ください。
車をリースした場合のメリットは?経費計上の方法はどうなる?
車をリースした場合には、リース料の支払い時に支払い分を支払手数料などとして経費計上することができます。
最近はカーシェアリングや車のサブスクを使っているような個人事業主も多いかもしれませんが、カーシェアリングも毎月の支払いをリース料と同じように扱えます。
リースの場合、減価償却費の計算や、資産計上などをしなくてよいので楽であることがメリットです。
また車検代をはじめとするメンテナンス費用がかからないのも、カーリースの大きなメリットです。
また、資金繰りという点においても、リースは、購入代金を一括で支払わなくてよいので、十分にメリットはあります。
一方で、節税効果としてメリットがあるかというと、特にメリットはありません。
一般的に購入した場合とリースの場合では、リースの方が維持費などが車両代のほかに上乗せされ、トータル支払額が多くなっているケースがあります。
そのため毎月の支払額が減価償却費よりも高くなり、結果として毎月の経費計上額が増える可能性はあります。
車がプライベート用と事業用の兼用でも経費計上できる!家事按分がポイント

個人事業主の方は、事業用の車をわざわざ買うということが難しく、プライベートと兼用になっていることも多いでしょう。
そういった場合でも、車関連の費用すべてを、事業利用割合分のみ経費計上することができます。これを家事按分とよびます。
では、車の家事按分をする際、事業利用割合をどのように求めるのでしょうか。
じつは、税法上、家事按分の割合の算出方法に決まりはありません。
ですので、客観的に税務署に証明できる方法を自分なりに考えて事業利用割合を算出する必要があります。
といっても、完全オリジナルの方法を使うことは、税務署に指摘されるリスクが高くなってしまうためおすすめできません。
広く一般的に使われている方法を利用しましょう。
一般的に使われている車の家事按分における事業割合算出方法は、走行距離を利用した按分です。
なお、ETC代や駐車場代などは、個別に事業で利用した都度集計しておきその時点で費用計上します。
そのほか、基本的に車を使って仕事をしており、平日は仕事でしか車を使わないけど、休みの日はプライベートでしか仕事をしないという個人事業主であれば、7分の5を経費とするといった方法も有効です。
家事按分におけるポイントは、あくまで客観的に証明できるように証拠を残しておくことです。
走行距離で家事按分をする場合には、走行記録をしっかりととっておきます。
また事業で車を使った場合の走行距離のほかに「営業目的」、「事業用の品の運搬目的」など、どういう目的で車を使ったかもしっかりと記録しておきましょう。
家事按分について詳しく知りたい方は、詳しい記事がありますのであわせてご一読ください。

確定申告は必ず青色申告を選択する
青色申告の届出をしていれば、プライベートと兼用の車に関する費用を、事業での利用割合が10%であっても、家事按分を利用して経費にすることができます。
一方で、青色申告の届出をしていない、いわゆる白色申告の場合には、事業利用割合が50%以上の費用以外は、家事按分できません。
さらに、青色申告の場合は、少額減価償却性資産の特例というものを使えますので、30万円以下の中古車を買った場合には、購入代金全額をその年の費用にすることもできます。
その他、青色申告においては、様々な節税上の優遇措置があるため、複式簿記が必須であるなどのデメリットも多少ありますが、節税のためにも必ず青色申告の届出をするようにしましょう。
なお、青色申告の届出は、新規開業の場合には、起業後2か月以内、白色申告からの変更の場合には、青色申告しようとする年の3月15日までに提出する必要があるので、忘れないようにしましょう。
車を使ったその他の節税方法
車は、購入費用まるまるを、購入してすぐに経費にすることができないため、購入によって節税をすることは難しいです。
しかし、車の買い替えのタイミングを、所得が多額に発生している年にするなどの調整により、売却損益を所得に入れ込むことで、節税につながる場合があります。
たとえば、所得が1000万円でている時に、減価償却後の簿価が500万円の車を100万円で売ることで、売却損400万円を所得の1000万円にぶつけて、所得を合計で600万円にすることができます。
またこのあたりの仕分け方法は下記のサイトが詳しいので、気になる方はチェックしてみてください。
おすすめのクラウド型会計ソフト3選
さて、そもそも皆さんは今現在どんな会計ソフトを利用していますか。
クラウド型の会計ソフトを使っていない人がもしいれば、経理の工数が相当減ると思いますので、クラウド型会計ソフトを絶対に導入すべきと断言できます。
クラウド型会計ソフトを使えば車の減価償却も簡単に経費にすることができます。
また、会計ソフト無しで確定申告しようなんて甘い考えをもっている人も、
「安い」クラウド型会計ソフトを導入して経理の時間削減を絶対にすべきです。
会計ソフトのコストよりも、クラウド型会計ソフトを利用することによる、経理時間や経理コストの削減効果の方が大きいからです。
| 弥生 オンライン  | マネー フォワード  | freee | |
| 個人 青色申告 | 初年度無料 年11,330円 ※やよいの青色申告 ※初年度無料キャンペーン 利用時翌年度の 年間利用料 【青色申告向け公式HP】 https://www.yayoi-kk.co.jp/…. | 初月無料 年11,880円 ※マネーフォワード 確定申告 ※最も安いプラン 【青色申告向け公式HP】 https://moneyforward.com/…. | 初月無料 年12,936円 ※個人事業主向け ※最も安いプラン 【青色申告向け公式HP】 https://www.freee.co.jp/ |
| 個人 白色申告 | 永久無料 ※やよいの白色申告 【白色申告向け公式HP】 https://www.yayoi-kk.co.jp/…. | 初月無料 年11,880円 ※マネーフォワード確定申告 ※最も安いプラン 【白色申告向け公式HP】 https://moneyforward.com/…. | 初月無料 年12,936円 ※個人事業主向け ※最も安いプラン 【白色申告向け公式HP】 https://www.freee.co.jp/ |
| 法人 | 初年度無料 年30,580円 【法人向け公式HP】 https://www.yayoi-kk.co.jp/…. | 初月無料 年39,336円 ※最も安いプラン 【法人向け公式HP】 https://moneyforward.com/…. | 初月無料 年39,336円 ※2024年7月以降 ※最も安いプラン 【法人向け公式HP】 https://www.freee.co.jp/ |
| 使いやすさ | 経験者向け | 経験者向け | 初心者向け |
| 機能面 | 機能充実 | 機能充実 | 機能充実 |
ちなみに、おすすめの会計ソフト、会計アプリの紹介記事もありますので、よろしければご覧ください。


格安で確定申告が可能な税理士
最後に、格安で確定申告を依頼できる税理士を紹介したいと思います。
節税のことや経費のことを自分で勉強するのは結構時間がかかります。
また、確定申告は非常に面倒な作業です。
ですので、税理士を安くつけることはできないかと誰もが考えます。
税理士は質で選んだほうが節税に結果的につながるから良いと税理士である筆者は主張したいところですが、
ほとんどの方は税理士を値段で選ばれているのも事実です。
そこで、個人の皆様にできる限り安い税理士サービスを紹介できないかと選んできたサービスがこちらになります。
まだ税理士をつけていない方は、少しくらい費用を払ってでもいいので税理士をつけることをおすすめします。
どれだけ自分で税金や経費のことを勉強していても、勘違いしてしまっていることは実は山ほどあります。
税金や経費に関する記事も間違いがよく見受けられます。
そういった勘違いや間違いを防ぐとともに、情報収集の手間を大幅に防げるのが税理士に依頼する最大のメリットなのです。
以下の税理士事務所は10万円前後で確定申告代行を依頼できる非常に格安な税理士事務所です。
みんなの会計事務所の確定申告代行

合計の収入が数百万円程度と低い方は、みんなの会計事務所の確定申告代行サービスを利用いただくと安くなる可能性が高いと思います。
ただし、仮想通貨の収入がある方で、海外の取引所を利用している方には対応していませんので注意してください。
よろしければ、お見積りをとってみてください。
税理士の探し方や各地域でのおすすめ税理士をご紹介
各地域でのおすすめ税理士や税理士の探し方などをご紹介している記事もあります。
よろしければ、参考にしてみてください。
-
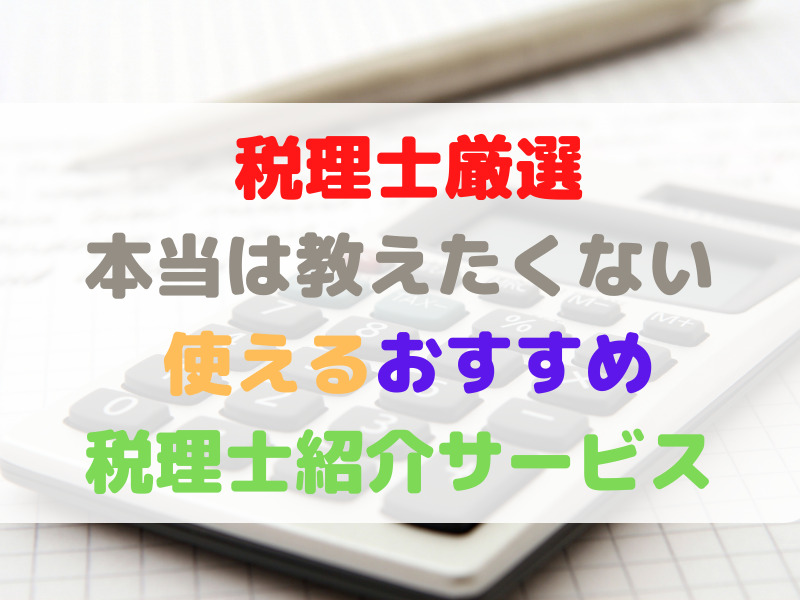
【税理士厳選】評判の良いオススメ税理士紹介サービスランキング8選【相続・個人事業主・中小企業経理担当者必見】
-
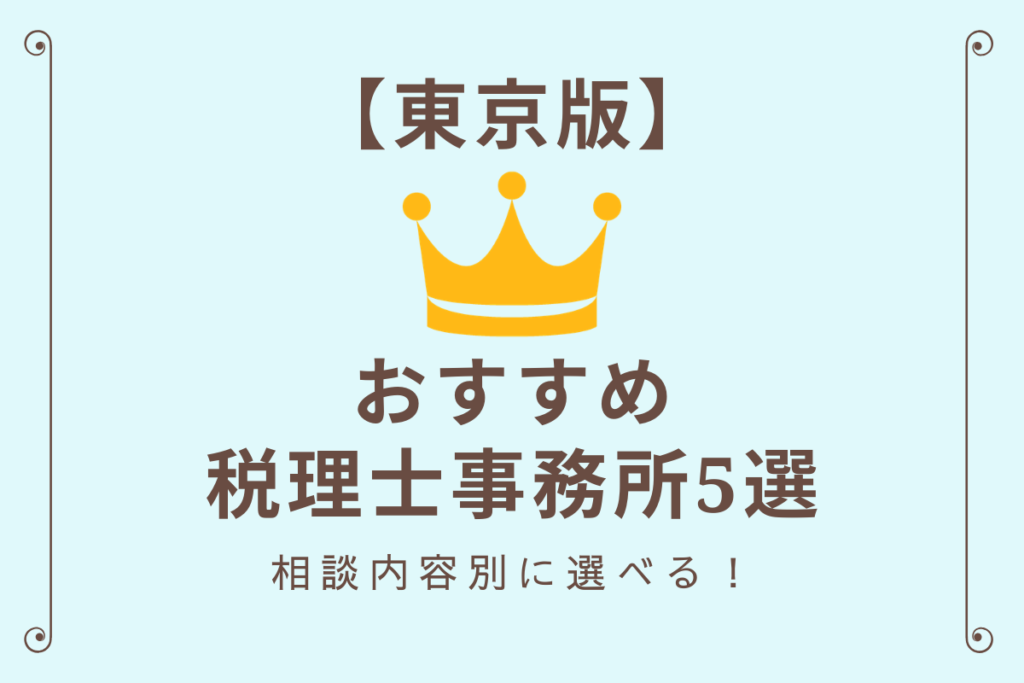
東京でオススメ評判の良い税理士事務所ランキング5選!相談内容(個人・法人・相続)別に解説【一覧から検索、口コミは有効?!】
-
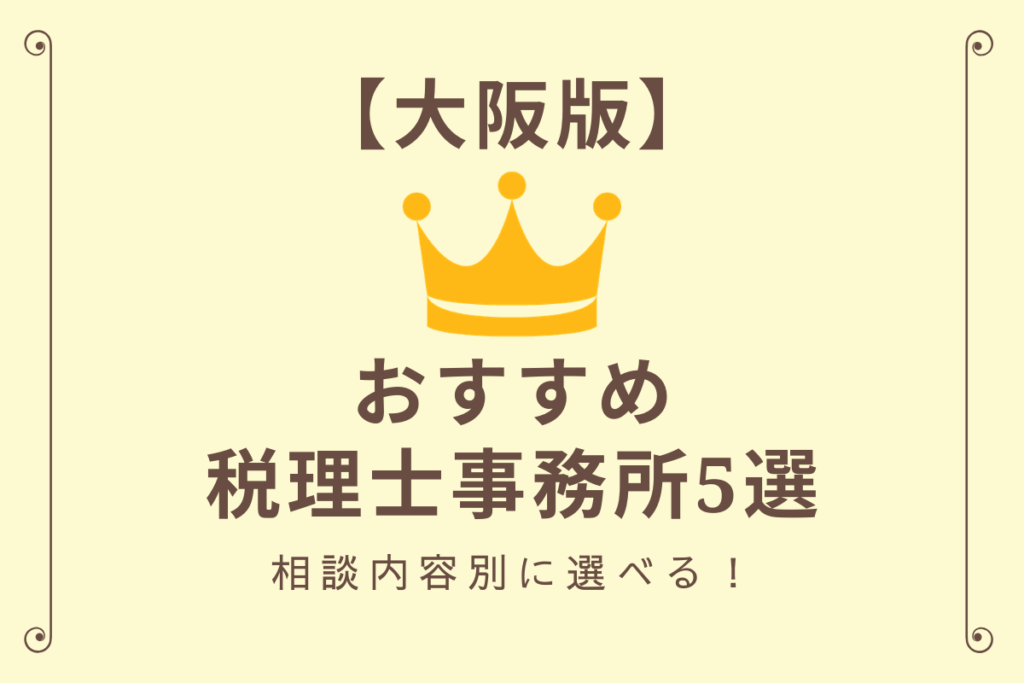
大阪で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続や確定申告・中小企業など相談内容別に比較!
-

【本当は教えたくない】税理士に無料で相談する方法6選【税理士が解説】個人事業主・相続税に悩んでいる方・経理担当者必見!!
-
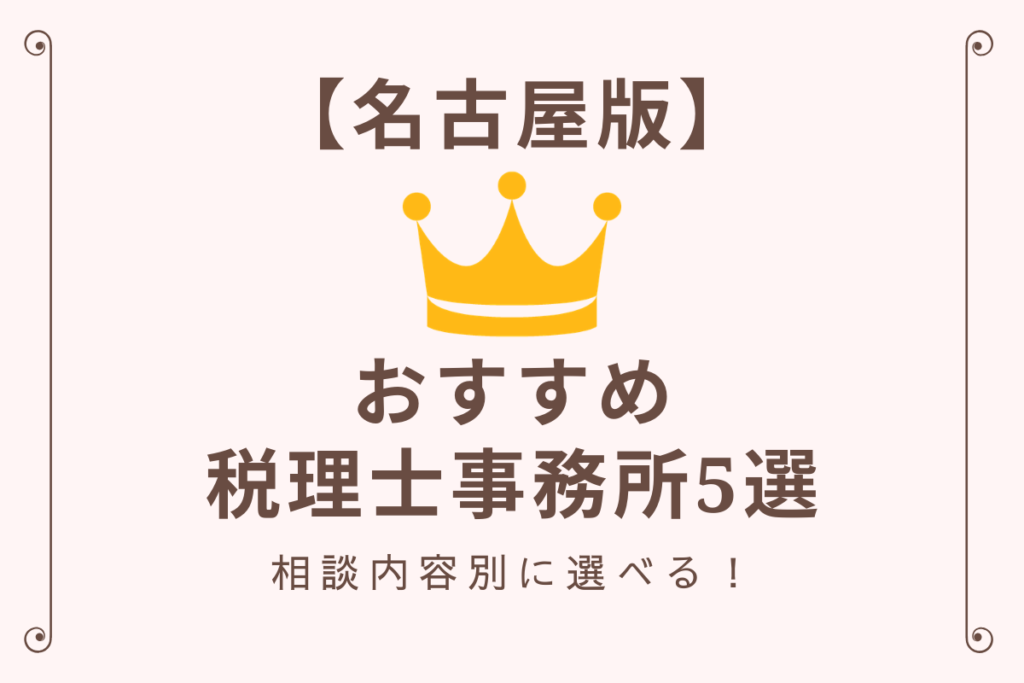
愛知県・名古屋で評判が良い税理士事務所オススメランキング24選!相続や確定申告など相談内容別に解説、比較!
-
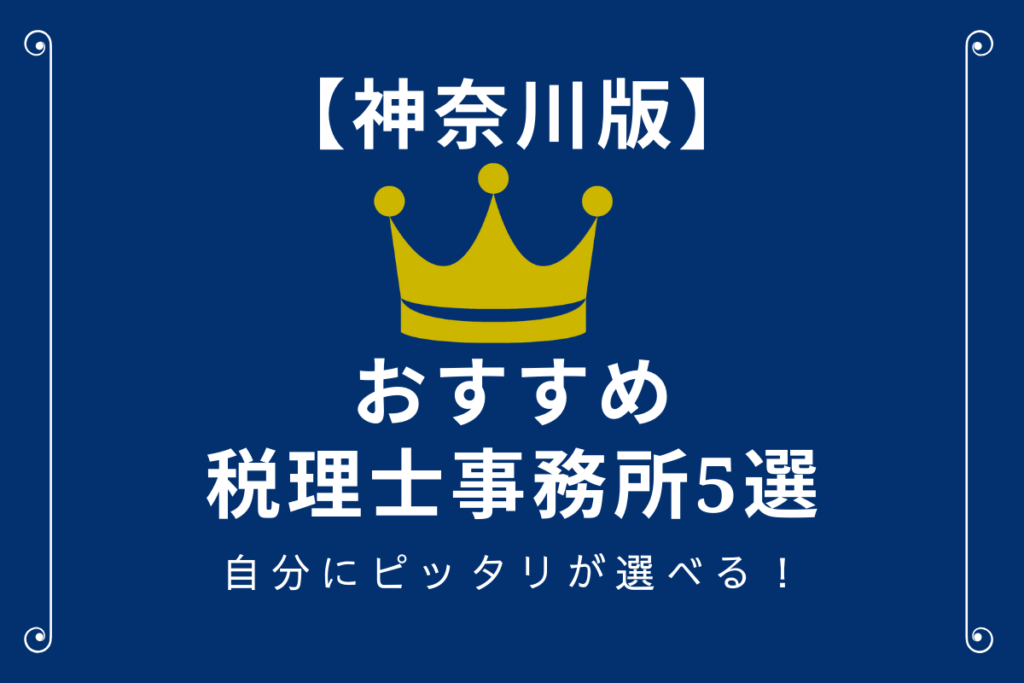
神奈川県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-
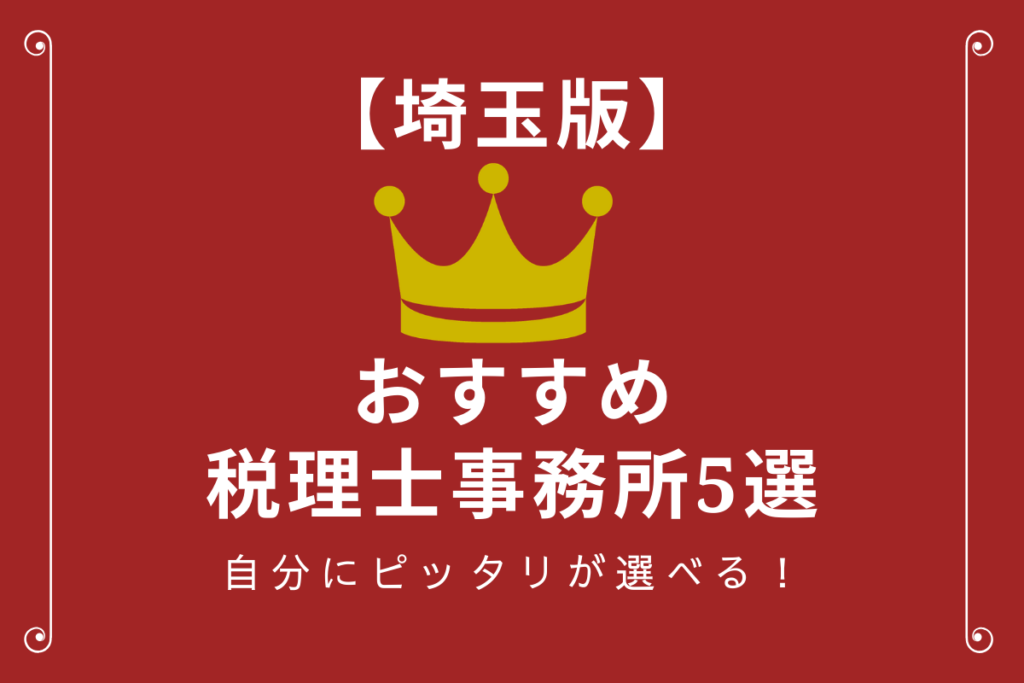
埼玉県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-
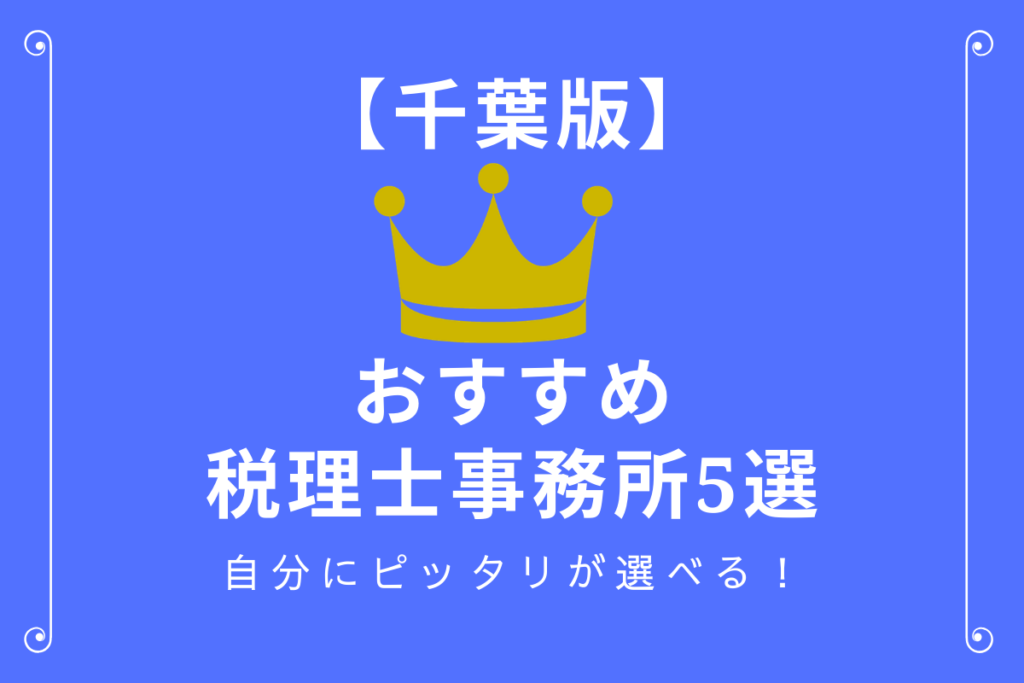
千葉県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

福岡県・福岡市で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相談内容(相続・個人・法人)別に比較、解説【税理士執筆】
-

兵庫県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング15選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

静岡県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

北海道で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

東京都世田谷区で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
業務で車を使う個人事業主にとって、車に関する費用を適正に経費にすることができるかどうかは、節税に相当有利になります。
車に関する経費を適切に計上し、事業を有利に進めましょう。