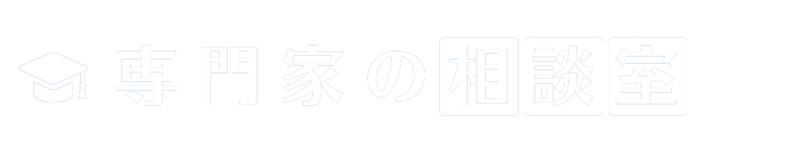事業主貸とは、事業に関係ない支出をした際に利用する勘定科目です。
法人の仕訳では出てこない勘定科目のため、簿記の勉強などではなかなか馴染みのない勘定科目になりますが、個人事業主の経費を考える上では、非常に重要です。
今回は、事業主貸の使い方について、仕訳例などを用いて、徹底解説いたします。
▼この記事でわかること
・事業主貸はプライベートの費用を処理する勘定科目
・事業主貸の仕訳例を確認してイメージをつけよう
・事業主貸が少ないと税務署に怪しまれる?!
生活費などのプライベートな支出は「事業主貸」という勘定科目で記帳
事業主貸は、生活費などの経費とはならないものを、事業用の口座や手元資金から支出した際に使用する勘定科目です。
経費とは、事業に関係する費用のことをいいます。
ようするに、事業に関係ない費用を仕事用のお金を使って払った場合は、事業主貸を使うと理解してもらってかまいません。
プライベートの費用を処理する勘定科目だと考えるとわかりやすいかもしれません。
「事業主貸」を使った具体的な帳簿イメージ【簿記で解説】
では、具体的に、どういった場合に事業主貸が発生するのでしょうか。
例えば、事業に使う目的で持っていたお金で食事のお会計をしたとしましょう。
メモ
(1)取引先の接待目的の食事
接待交際費 / 現金預金
メモ
(2)プライベートの食事
事業主貸 / 現金預金
このような仕訳の違いになります。
イメージがわきましたでしょうか?
このように、事業主貸という勘定科目は、経費にならないものを処理するために存在しているため、経費になるもの、ならないものをしっかり理解することが重要です。
また、事業用とプライベート用でお金を普段から分けておくことも非常に重要です。
事業用のクレジットカード、銀行口座、電子マネーなどを用意しておくことをおすすめします。
経費にならないもの(事業主貸になるもの)を徹底解説
続いて、経費にはならず事業主貸となるよくある例をご紹介します。
メモ
(1)事業用預金口座から生活費のためのお金10万円をおろした
事業主貸 10万円 / 現金預金 10万円
事業用口座から生活費をおとした場合は、経費にはならないため、事業主貸で処理します。
メモ
(2)事業用のクレジットカードでプライベート目的の品物を5万円分購入した
事業主貸 5万円 / 未払金(もしくは現金預金) 5万円
事業用のクレジットカードで生活用品などの経費にならないものを購入した場合には、事業主貸で処理します。
メモ
(3)事業用預金口座から事業主自身の給料40万円を支払った
事業主貸 40万円 / 現金預金 40万円
事業主自身の給料は、経費にはできないため、事業主貸で処理します。
また、事業主と生計を一にする配偶者などの給料も原則として経費にはできないため、事業主貸で処理します。
ただし、青色事業者専従者給与の届出を出した家族などで条件を満たす場合には給与を経費にすることができます。
メモ
(4)事業用口座から国民健康保険、国民年金などを合計30万円支払った
事業主貸 30万円 / 現金預金 30万円
国民年金保険、国民年金などの支払いは、経費にならないため、事業主貸で処理します。
ただし、社会保険料控除などの制度を利用することで、所得税、住民税は節約できる場合がありますので、確認してみましょう。
メモ
(5)事業用口座から、個人事業主自身の税金を合計20万円支払った
A.住民税、所得税、プライベート用の自動車税、加算税、延滞税、相続税、贈与税、交通違反等の罰金
事業主貸 20万円 / 現金預金 20万円
B.事業税、事業利用資産の固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、事業所税
租税公課 20万円 / 現金預金 20万円
Aの住民税などの個人事業主自身に帰属するような税金の支払い、罰金などの支払いは経費にはできないため、事業主貸で処理します。
一方で、Bの事業税などの事業に関連して発生する税金に関しては、経費とすることができるため、租税公課で処理します。
税金に関しては、少し複雑なため、経費にできるものとできないものをしっかり確認して、処理するようにしましょう。
メモ
(6)自宅兼事務所の家賃
家事按分により、一定割合を事業主貸で処理
自宅の一部を事務所として使っている個人事業主の場合、家賃については、そのすべてを経費にすることはできません。
しかし、一定割合を経費とし、残りを事業主貸として処理することが可能です。これを家事按分とよびます。
ではこの割合はどのように決めるのでしょうか?実は税法上の決まりはありません。
したがって、一定の理屈が通るような、客観的に妥当だと思われるような割合を自ら決定する必要があります。
具体的には、以下のような方法で按分することが考えられます。
ポイント
・自宅兼事務所の家賃、固定資産税、住宅ローンの利子など
業務に利用している面積割合を経費として処理し、残りを事業主貸として処理
・水道光熱費、通信費
業務に利用している日数、時間などの割合を経費として処理し、残りを事業主貸として処理
・ガソリン代
業務に利用している走行距離、時間などの割合を経費として処理し、残りを事業主貸として処理
【具体例】
自宅兼事務所として100平米の賃貸マンションを年間家賃400万円で賃貸している。業務は書斎である20平米の部屋で行っている。
この例では、経費とできる割合は、20平米÷100平米=20%となるため、
地代家賃として処理できるのは、400万円×20%=80万円。
残りの320万円は、事業主貸として処理する。
仕訳は以下のようになる。
- 事業主貸 320万円 / 現金預金 400万円
- 地代家賃 80万円
このあたりの家事按分について、別記事についてわかりやすくまとめていますのであわせてお読みください。

事業主貸は翌事業年度スタート時に事業主借と相殺され元入金に
事業主貸という勘定科目は、事業主借、元入金という勘定科目と密接に関係しています。
ここでは、事業主借、元入金とその関係性について説明します。
元入金とは資本金のようなもの
元入金(もといれきん)とは、法人でいう資本金のことで、事業を行うための軍資金のようなイメージで考えておくとよいでしょう。
なお、資本金とは違って、元入金は毎年変動しますので、その点に注意が必要です。
事業主借とは事業主貸の逆バージョン
事業主借とは、事業主貸の逆にあたるもので、事業に必要なお金を事業主個人の財布から支払う時に使われます。具体例として以下のようなものがあります。
メモ
(1)プライベート用の財布で、事業に使うための消耗品を5万円分買った
消耗品費 / 事業主借
メモ
(2)プライベート用口座から事業用口座に資金を移した。
現金預金 / 事業主借
メモ
事業用口座に利息がついた
現金預金 / 事業主借
事業用口座であっても利息は、個人の所得としてあつかわれます。ただし、利息に関しては源泉徴収がされ税金はすでに支払われているため、申告の必要はありません。
メモ
サラリーマン兼個人事業主のサラリーマンとしての給料が、事業用口座に振り込まれた
現金預金 / 事業主借
この場合は、手取りとして実際に口座残高が増えた額についてののみ仕訳をきることに注意してください。
事業主貸に関する具体的な年度末の記帳方法
では、具体的に確定申告時にどのような処理がなされるのか見ていきましょう。
ある個人事業主は1年目に100万円を元手に事業をはじめたとしましょう。
1年目の事業運営の結果、事業主貸が30万円計上され、事業主借が20万円計上されました。また、利益(所得金額)が40万円発生しました。
2年目の事業年度スタート時の元入金は、以下のように計算することができます。
100万円―30万円+20万円+40万円=130万円
したがって、2年目は130万円の元入金からスタートすることになります。
仕訳にすると以下のようになります。
メモ
(1)事業スタート時
現金預金 100万円 / 元入金 100万円
メモ
(2)翌事業年度スタート時
事業主借 20万円 / 事業主貸 30万円
損益 40万円 元入金 30万円
法人の資本金は、基本的には決算をまたいでも変動しませんが、個人事業主の資本金にあたる元入金は、決算を迎えるごとに変動する点が法人の資本金と大きく異なります。
なお、事業主貸が多額に発生した場合は、元入金がマイナスとなることがありえますが、マイナスであってもかまいません。
事業主貸と事業主借の使い分けを間違えても問題なし
事業主貸勘定と事業主借勘定、どちらを使うの?
ふとした時に迷うかもしれません。
ポイント
- 事業主貸は、事業主にお金を貸すときに使う
- 事業主借は、事業主にお金を借りるときに使う
と、間に「に」をいれておくと覚えておくと便利です。
しかし仮に使い分けを間違ったとしても問題ありません。
事業主貸は帳簿上、借方に必ずきますし、事業主借は帳簿上必ず貸方にきますので、集計した際に、どちらであったとしてもプラスマイナスの値には影響をおよぼさないからです。
なお最終的に1年を通して元入金がプラスになっていれば、その1年は健全な事業運営ができているといえます。
青色申告では事業主貸、事業主借は貸借対照表に記入
個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告があります。
青色申告の方が青色申告特別控除など節税メリットを多く受けられるためおすすめですが、青色申告は、複式簿記が義務付けられており、損益計算書と貸借対照表の記入が求められます。
事業主貸、事業主借は貸借対照表の勘定科目にあたるため、青色申告においては、事業主貸、事業主借を記入する箇所があります。
1年間の合計の事業主貸と事業主借を該当の欄に記入するようにしましょう。
税務調査での事業主貸、経費のチェックポイント
確定申告までには、1年間を通して使った支出を事業主貸と経費にしっかり区分して、申告する必要があります。
そして、申告した売上から申告した経費を差し引いた所得に対して税金を納める必要があります。
しかしこの確定申告は自己申告である、個人事業主の裁量にゆだねられてしまいます。
そのため税務署は抜き打ちで税務調査を行い、適正な確定申告がなされているのかチェックをしにくる場合があります。
ここでは、税務調査のチェックポイントを解説します。
売上に対して、経費が多いのか少ないのかは重要ではない!
売上に対して、経費が比較的多いと税金を納める額は極端に減ります。
だからといって、経費が多い個人事業主は税務調査で指摘されやすいのかと聞かれれば、答えはノーです。
事業に関係するものを適切に経費としていれば、税務調査が入ったとしても、経費は上限なく認められますので安心してください。
経費が事業に関係するものであるということを、客観的に証明できるように、領収書、レシート、クレジットカードの明細、メモなどの証拠をきっちりと用意しておきましょう。
税務調査が入ったら事業主貸はすべてチェックされる?
税務調査が入ったら、経費として適切なものがあがっているか、すなわち、事業主貸として計上すべきものが経費に入っていないかを主にチェックされます。
したがって、事業主貸の中身よりは、経費の中身を細かくチェックされることになります。
税務署の判断基準となる事業主勘定
そもそも税務調査に入る前に、税務署はある程度、脱税の疑いがある部分のめぼしをつけてきているケースが多々あります。
ここでは、事業主勘定に関して、税務署の目のつける判断基準を解説します。
事業主貸が少ない場合
事業主貸が少なく、かつ所得が少なかった場合、生活費をどうまかなっているのかと疑われます。
過去に十分な貯金をためていて、その貯金を取り崩して生活しているのであれば問題ないですが、売上を過少計上している疑いや、過去に申告していなかった疑いなどがあれば、税調調査が入る可能性が高まります。
事業主貸が多い場合
事業主貸が多く、かつ所得が少なかった場合、所得が本当はもっと多いのではないかと疑われます。
事業主貸により、事業用口座からの多額の出金があったり、生活費の支出があれば、「本当はもっと稼いでいるから生活費をかけているんじゃないか」、「所得をごまかしているのではないか」と疑われるというわけです。
事業主借が多い場合
事業主借が多い場合、プライべートなお金がなぜそんなにあるのかを疑われます。
事業主借が多いということは、プライベートな貯金が多額にあったことの証明になるため、その貯金をためるときに何か脱税などの行為があったのではないかと疑ってくるわけです。
また、事業主借が多い場合、贈与税の疑いもかけられる場合があります。
過去の給料所得や、貯金の推移などから、どう考えても、プライベートな貯金は少ないと考えられていた人が、多額の事業主借勘定を発生させていた場合、親や友人からお金をもらったのではないかと疑われるということです。
もし、一時的にお金を貸してもらっていた場合などは、親子間であっても簡単な借用書を用意し、借入であることを証明できるようにしておくと贈与税はかかりませんので、そういった対策をおすすめします。
ちろん正しく確定申告をおこなうためにも、また節税を考えるうえでも正しい経費の理解は不可欠です。
このあたりは経費に関して詳しく解説している記事がありますので、こちらをご一読ください。
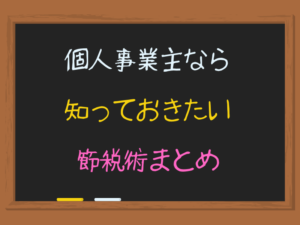
マネーフォワードやfreeeなどのクラウド型会計ソフトを使うのがおすすめ
お伝えしたように、事業主貸と経費をしっかりと区分して仕訳をきることは非常に重要です。
仕訳をスムーズにきることや確定申告書をミスなく提出できるようにサポートしてくれる会計ソフトとして、
マネーフォワードやfreeeなどのクラウド型会計ソフトが人気になってきており、筆者もおすすめしています。
これらのクラウド型会計ソフトは、クレジットカードの明細や預金口座明細との自動同期などができるので、非常に楽に経費や事業主貸の仕訳をきることができます。
特にプライベート用と事業用のクレジットカードや預金などを分けていない人にとっては、このクラウド型会計ソフトの方が網羅的に処理ができて便利と感じることでしょう。
また、年度の繰越処理は自動で行われるため、事業主借と事業主貸の相殺や元入金への加減が自動でなされます。
さらに、クラウド上にデータがあるため、税理士と直接会うことなく、アドバイスをもらうことも可能です。
おすすめのクラウド型会計ソフト3選
安くて機能も充実しているクラウド型会計ソフトは実は3つしかありません。
| 弥生 オンライン  | マネー フォワード  | freee | |
| 費用面 (税込) | 初年度無料 年11,330円 ※やよいの青色申告 ※初年度無料キャンペーン利用時翌年度の年間利用料 | 初月無料 年11,880円 ※マネーフォワード確定申告 ※最も安いプラン | 初月無料 年12,936円 ※個人事業主向け ※最も安いプラン |
| 使いやすさ | 経験者向け | 経験者向け | 初心者向け |
| 機能面 | 機能充実 | 機能充実 | 機能充実 |
| 公式HP | https://www.yayoi-kk.co.jp/ | https://moneyforward.com/ | https://www.freee.co.jp/ |
ちなみに、おすすめの会計ソフト、会計アプリの紹介記事もありますので、よろしければご覧ください。


格安で確定申告が可能な税理士
最後に、格安で確定申告を依頼できる税理士を紹介したいと思います。
節税のことや経費のことを自分で勉強するのは結構時間がかかります。
また、確定申告は非常に面倒な作業です。
ですので、「税理士を安くつけることはできないか」と誰もが考えます。
税理士は質で選んだほうが節税に結果的につながるから良いと税理士である筆者は主張したいところですが、
ほとんどの方は税理士を値段で選ばれているのも事実です。
そこで、個人の皆様にできる限り安い税理士サービスを紹介できないかと選んできたサービスがこちらになります。
弊社が調べた限り、このサービスより安く確定申告を依頼できるところはありませんでした。
まだ税理士をつけていない方は、少しくらい費用を払ってでもいいので税理士をつけることをおすすめします。
どれだけ自分で税金や経費のことを勉強していても、勘違いしてしまっていることは実は山ほどあります。
税金や経費に関する記事も間違いがよく見受けられます。
そういった勘違いや間違いを防ぐとともに、情報収集の手間を大幅に防げるのが税理士に依頼する最大のメリットなのです。
以下の税理士事務所は10万円程度で確定申告代行を依頼できる非常に格安な税理士事務所です。
みんなの会計事務所の確定申告代行

合計の収入が数百万円程度と低い方は、みんなの会計事務所の確定申告代行サービスを利用いただくと安くなる可能性が高いと思います。
ただし、仮想通貨の収入がある方で、海外の取引所を利用している方には対応していませんので注意してください。
よろしければ、お見積りをとってみてください。
税理士の探し方や各地域でのおすすめ税理士をご紹介
各地域でのおすすめ税理士や税理士の探し方などをご紹介している記事もあります。
よろしければ、参考にしてみてください。
-
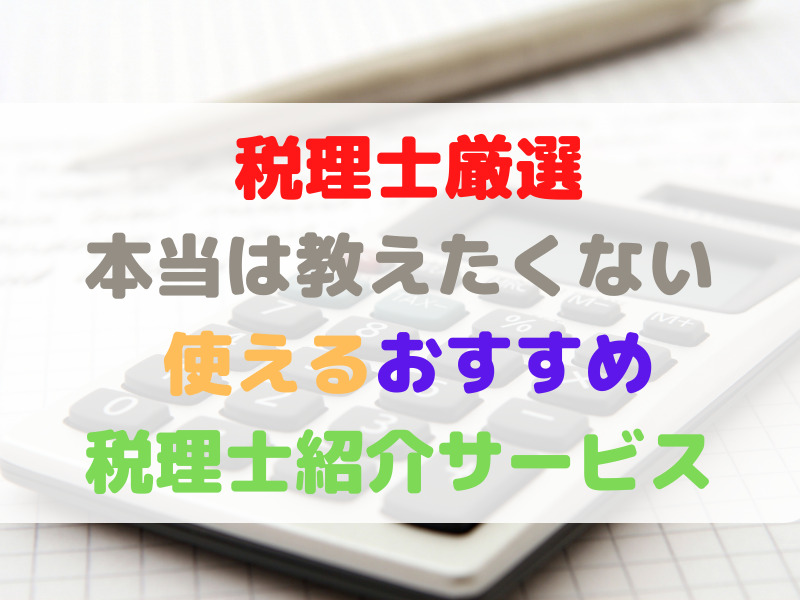
【税理士厳選】評判の良いオススメ税理士紹介サービスランキング8選【相続・個人事業主・中小企業経理担当者必見】
-
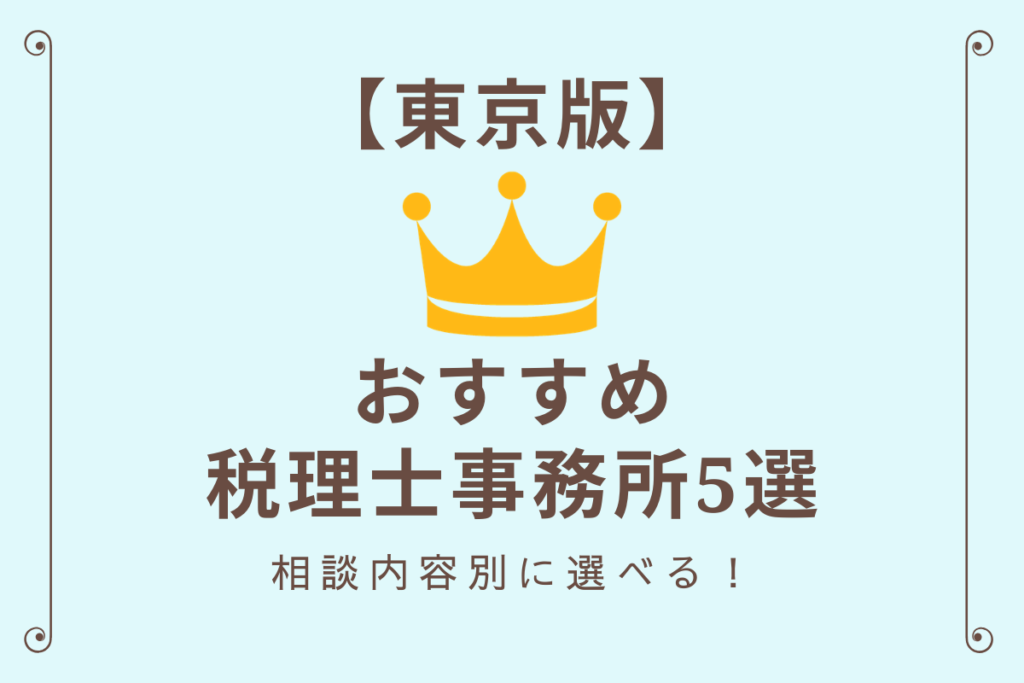
東京でオススメ評判の良い税理士事務所ランキング5選!相談内容(個人・法人・相続)別に解説【一覧から検索、口コミは有効?!】
-
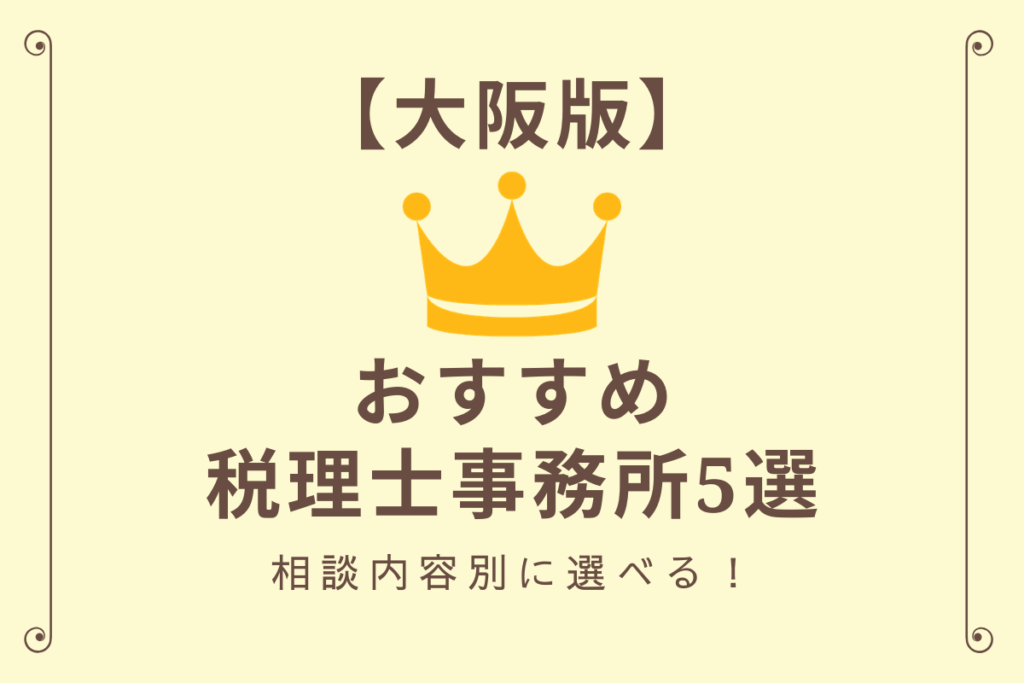
大阪で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続や確定申告・中小企業など相談内容別に比較!
-

【本当は教えたくない】税理士に無料で相談する方法6選【税理士が解説】個人事業主・相続税に悩んでいる方・経理担当者必見!!
-
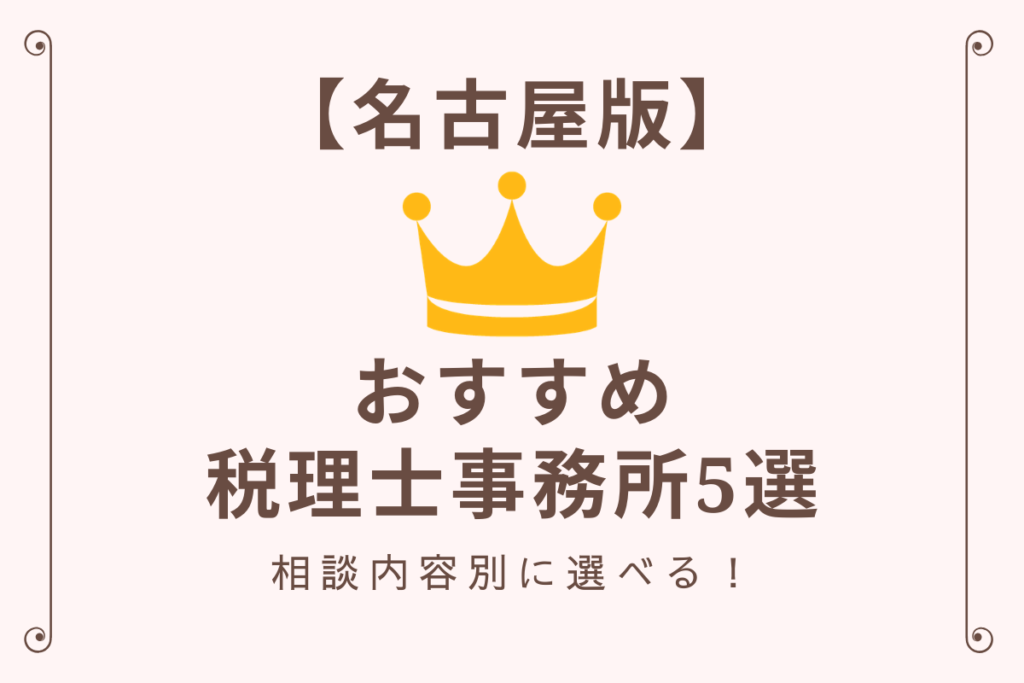
愛知県・名古屋で評判が良い税理士事務所オススメランキング24選!相続や確定申告など相談内容別に解説、比較!
-
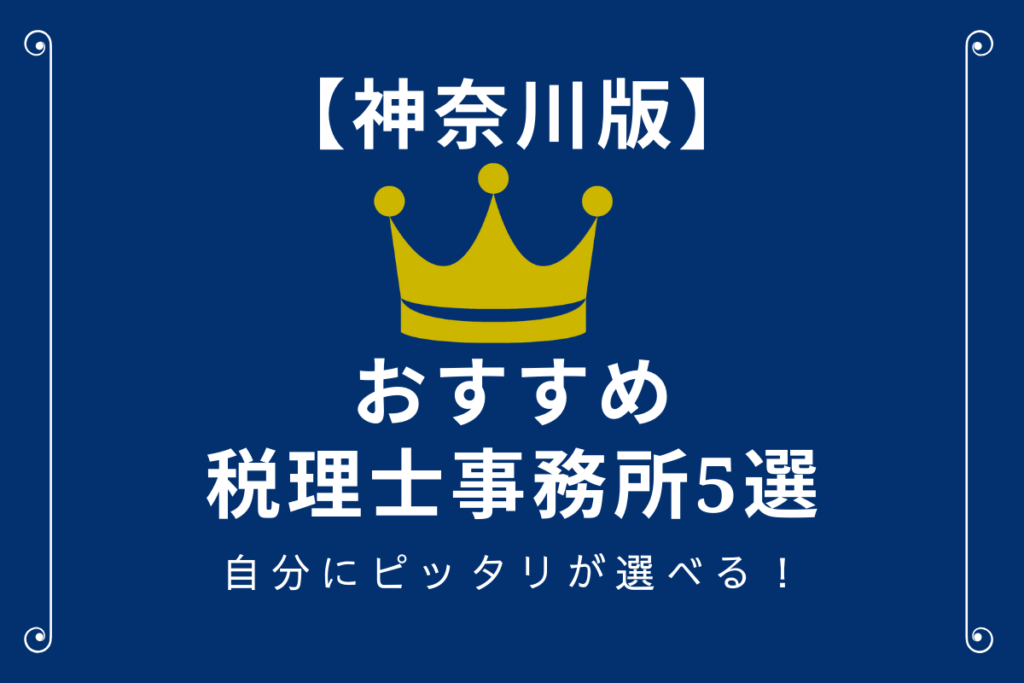
神奈川県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-
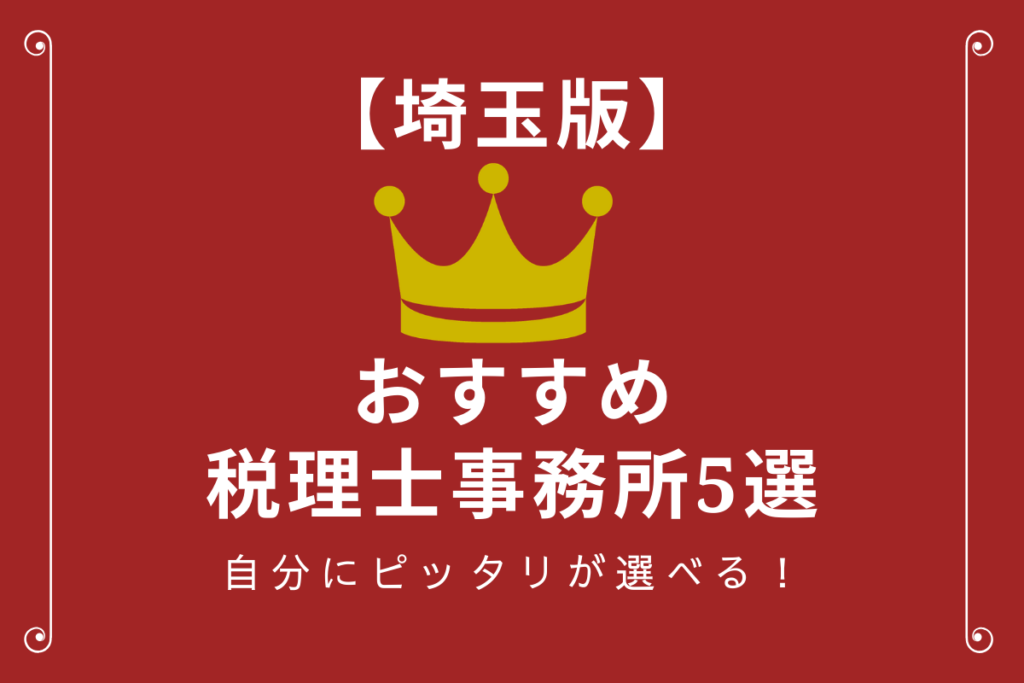
埼玉県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-
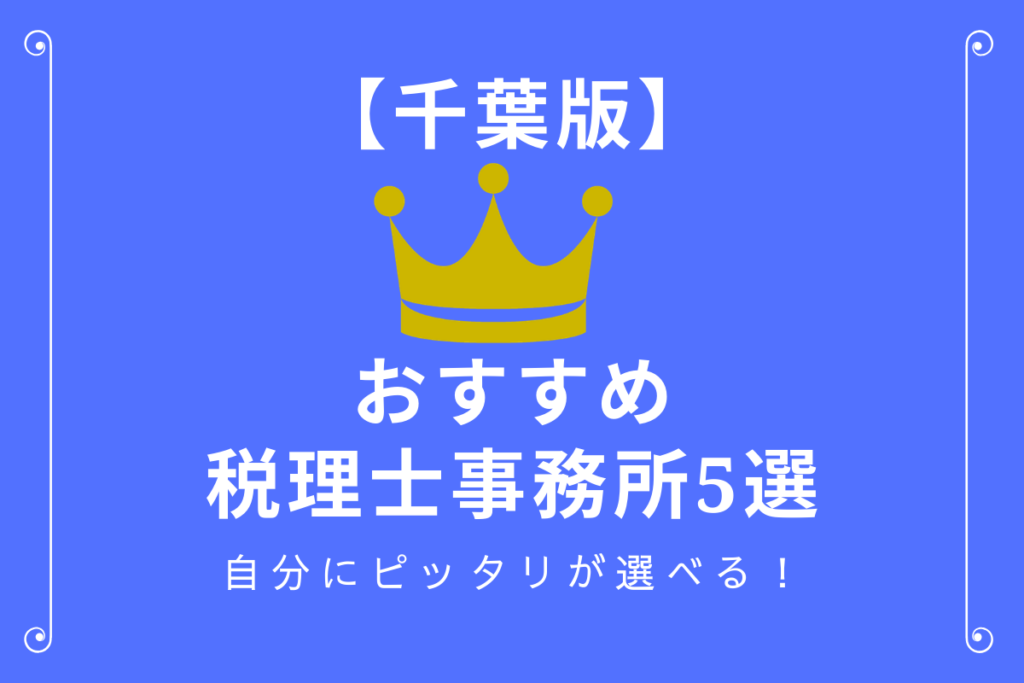
千葉県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

福岡県・福岡市で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相談内容(相続・個人・法人)別に比較、解説【税理士執筆】
-

兵庫県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング15選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

静岡県で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

北海道で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
-

東京都世田谷区で評判が良いオススメの税理士事務所ランキング5選!相続、確定申告、中小企業に分けて解説、比較!
まとめ
事業主貸は、経費になるもの、ならないものをしっかり区分する上で非常に重要な勘定科目です。
経費になるもの、ならないもののポイントをしっかり理解し、仕訳において事業主貸を使いこなしましょう。
事業主貸、経費を理解することによって、賢く節税し、健全な個人事業の運営が実現されることでしょう。